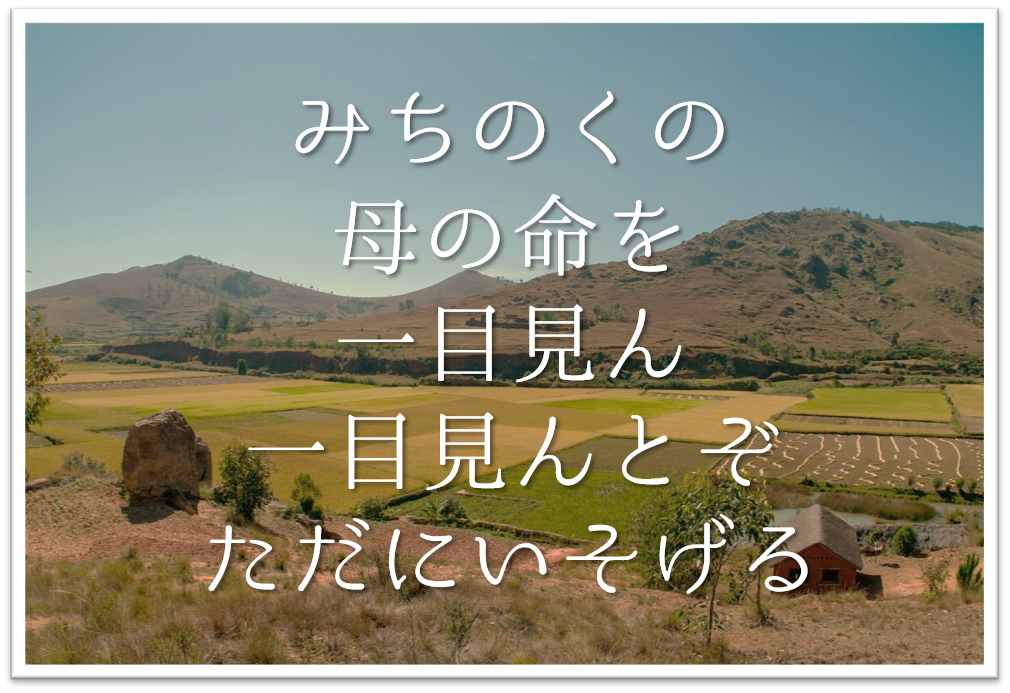
日本人は五・七・五・七・七のしらべで、生活の中の様々な感情、人生に対する想い、美しい自然を詠んできました。
歌を詠むことを本業にするのではなく、他に本業を持ちつつ、歌人として成功した人も多くいます。
今回は、精神科医をつとめる傍ら、歌人としての名声も得た斎藤茂吉の名歌「みちのくの母の命を一目見ん一目見んとぞただにいそげる」をご紹介します。
斎藤茂吉 みちのくの 母のいのちをひと目見ん ひと目見んとぞ ただにいそげる pic.twitter.com/XD66HX953F
— 海野はる香@和歌・短歌&相互 (@12345_Sugimoto) February 15, 2017
本記事では、「みちのくの母の命を一目見ん一目見んとぞただにいそげる」の意味や表現技法・句切れについて徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる」の詳細を解説!

みちのくの 母の命を 一目見ん 一目見んとぞ ただにいそげる
(読み方:みちのくの ははのいのちを ひとめみん ひとめみんとぞ ただにいそげる)
作者と出典
この歌の作者は、「斎藤茂吉(さいとうもきち)」です。山形県で生まれ、東京の医師の家に養子として入り、医業のかたわら短歌も詠んだ人物です。
この歌の出典は大正2年(1913年)刊行された、斎藤茂吉の処女歌集『赤光(しゃっこう)』です。
この歌は、「死にたまふ母」という連作短歌として発表され、当時の歌壇に大きな話題を呼びました。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「東北にいる母のいのちのあるうちに、一目でも会いたい、一目でも会いたいという一心で急いで故郷へ向かうことだ。」
となります。
斎藤茂吉は15歳で養子に出され、故郷である山形の金瓶村から上京して開業医である斎藤紀一に引き取られて成長しました。
しかし、大正2年(1913年)、31歳東大医科大学助手となっていた茂吉のところに、山形の生母が危篤状態に陥ったとの知らせが入り、斎藤茂吉は薬を携え、急ぎ帰郷することになります。
この歌は、そんな帰郷の途上で詠まれた歌になります。
文法と語の解説
- 「みちのくの」
「みちのく」は、東北地方のことです。斎藤茂吉の生家は、山形県南村山郡金瓶村(現在の山形県上山市)にありました。
「の」は格助詞です。
- 「母のいのちを一目見ん一目見んとぞ」
「の」「を」は格助詞です。
「見ん」とは、「見む」のことで、動詞「見る」の未然形「見」+意志の助動詞「む」の終止形です。
「と」は格助詞。「ぞ」は、係助詞で、文末が連体形になる係り結びを作ります。
- 「ただにいそげる」
「ただに」は副詞で、「ひたすらに」という意味です。「いそげる」は、動詞「いそぐ」の連体形「いそげる」です。前の句に、係助詞「ぞ」があるので、係り結びで連体形になっています。この係り結びは、文意を強める働きがあり、いのちあるうちに一目でも母に会いたいという気持ちを強く表しています。
「みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、歌の中の大きな意味の切れ目のことです。
この歌は句切れがありませんので、「句切れなし」となります。
死に瀕している母のもとへ早く駆け付けたいという気持ちそのままに一息に詠まれています。
表現技法
この歌に用いられている表現技法は特にありません。
「みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる」が詠まれた背景

この歌は、斎藤茂吉の第一歌集『赤光』の中の、「死にたまふ母」という連作の中の一首です。
斎藤茂吉は、山形県の農村に生まれ、15歳の時に、東京の斎藤家に養子として引き取られました。養父斎藤紀一は医師で、斎藤茂吉も医師になるべく勉学に励み、東京帝国大学医科大学で学びました。
東大医科大学助手として研究を続けつつも、病院勤務も行っていましたが、大正2年(1913年)、山形の実家の生母が危篤であるとの報を受け、急ぎ帰郷します。
連作「死にたまふ母」は、帰郷後の母との最期の時間、葬送、喪失の哀しみを詠んだ59首に及ぶ連作短歌です。
「みちのくの…」の歌は、連作「死にたまふ母」の3首目にあたります。母危篤の報を受け、故郷山形へと急ぐ様子を詠んだ歌です。
この連作は最初、文芸雑誌『アララギ』に発表されたものです。『アララギ』初出の時、歌集『赤光』の初版では、この歌の結句は「いそぐなりけれ」となっていました。
改選版『赤光』で結句が「ただにいそげる」という言葉にあらためられました。
「いそぐなりけれ」よりも、「ただにいそげる」の方が、「ただに」という副詞も加わり、ひたすらに急ぐ気持ち、焦りや祈りに似た思いがより一層伝わってきます。
「みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる」の鑑賞

「みちのくの…」の歌は、養子に出され、離れて暮らしていた生母を思う気持ちにあふれた一首です。
「一目見ん一目見ん」という繰り返しから、作者の急ぐ様子、焦り、母の命あるうちに一目会いたいという祈りのような気持がせつせつと伝わってきます。
平明な言葉が使われ、率直な詠いぶりで、作者の心情が読者にもストレートに伝わってきます。
茂吉は寒村の農家の母のもとを離れ、医師となろうとしていました。医師として母を救いたい思いもあったでしょう。しかし、その一方で医師であればこそ状況の深刻さ・望みの薄さを察しての覚悟もあったかもしれません。
この歌が収められている斎藤茂吉の連作「死にたまふ母」は、近代短歌における挽歌の中でも特に高い評価を得ています。
(※挽歌(ばんか)・・・人の死を悼む歌のこと)
母を亡くす哀しみに対する癒しや慰めを連作「死にたまふ母」に見出す人は数多くおり、今尚多くの人々の共感を得ています。
作者「斎藤茂吉」を簡単にご紹介!

(1952年頃の斎藤茂吉 出典:Wikipedia)
斎藤茂吉は、明治15年(1882年)、山形県南村山郡金瓶村に守屋伝右衛門熊次郎の三男として誕生しました。
守屋家は、経済的な事情で三男茂吉に十分な教育を施すことができないと考え、同郷のよしみを頼り、東京で開業医をしていた斎藤紀一のところへ茂吉を養子に出します。のちに茂吉は、東京帝国大学医科大学に進んで医師となり、斎藤家の娘輝子と結婚、精神科医としても大成しました。
山形の寒村から上京した少年茂吉は、今まで全く知らなかった都会の生活の中で成長していくこととなりますが、開成中学に在学中に文学に親しみ、旧制第一高校時代に正岡子規の遺歌集『竹の里歌』に傾倒、短歌を詠むようになります。正岡子規の門弟の伊藤佐千夫に師事、雑誌『アララギ』で歌を詠みました。
正式に医師となる一方で、第一歌集『赤光』が話題作となり、斎藤茂吉は医業と短歌という二つの道を進むこととなりました。
その後、斎藤茂吉は精神科を専門とし、ヨーロッパへ留学し、青山脳病院院長としても働きました。研究熱心で、医学論文も多くものしています。
短歌の方も、アララギ派の歌人として『赤光』以降、多くの歌集や随筆集を発表し、古典文学研究の論文の発表もしました。
昭和28年(1953年)、70歳で病没しました。
「斎藤茂吉」のそのほかの作品

- ただひとつ 惜しみて置きし 白桃の ゆたけきを吾は 食ひをはりけり
- 沈黙の われに見よとぞ 百房の 黒き葡萄に 雨ふりそそぐ
- 猫の舌の うすらに紅き 手ざはりの この悲しさを 知りそめにけり
- 死に近き 母に添寝の しんしんと 遠田のかはづ 天に聞ゆる
- ものの行 とどまらめやも 山峡の 杉のたいぼくの 寒さのひびき
- 信濃路は あかつきのみち 車前草も 黄色になりて 霜がれにけり
- うつせみの 吾が居たりけり 雪つもる あがたのまほら 冬のはての日












