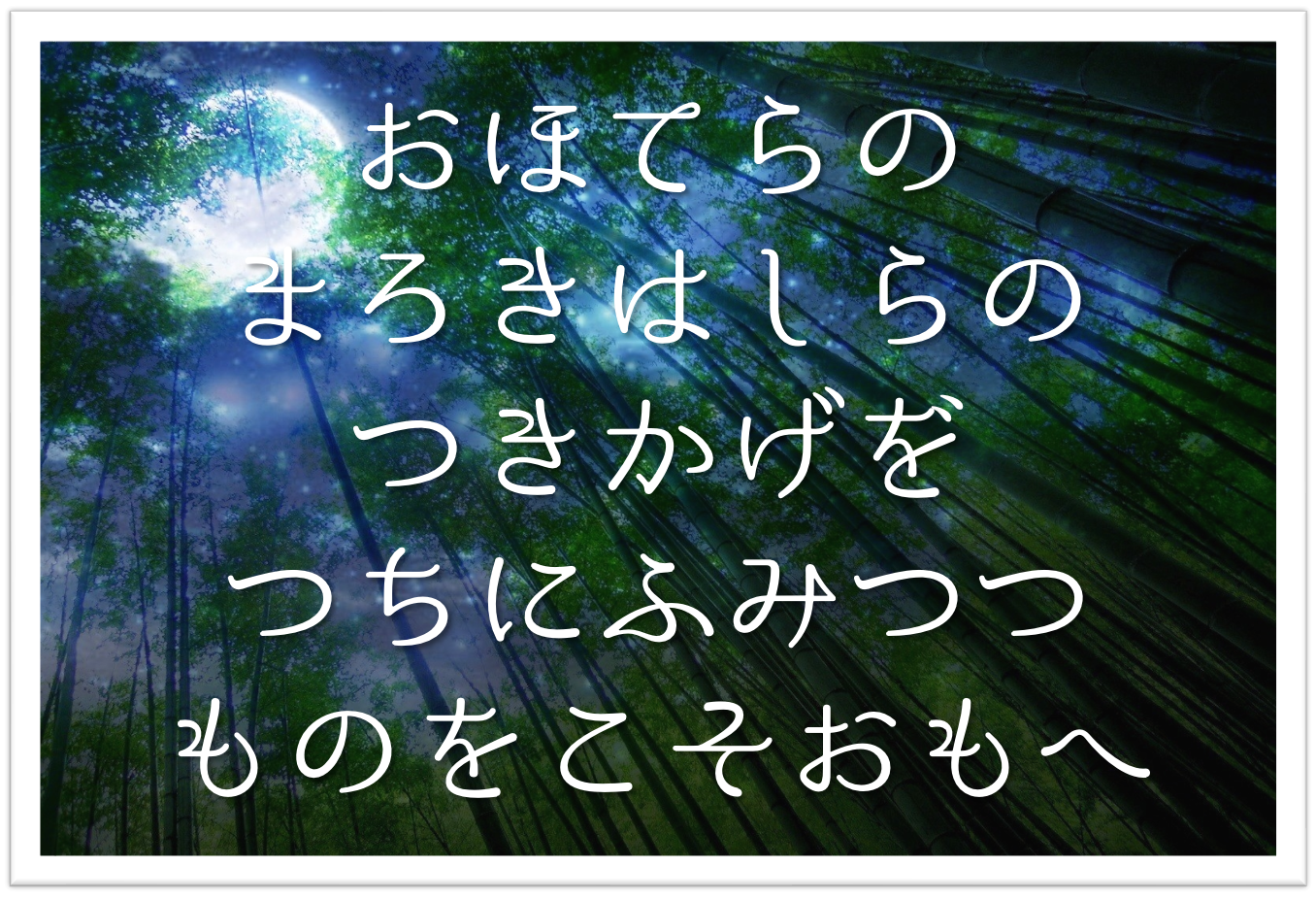
今回は、会津八一の歌「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」をご紹介します。
會津八一 歌人 「おほてら の まろき はしら の つきかげ を つち に ふみ つつ もの を こそ おもへ」 全部ひらがなの人で覚えてました。 #作家の似顔絵 pic.twitter.com/rraqQyZimx
— イクタケマコト:イラストレーター (@m_ikutake2) September 1, 2014
本記事では、「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」の詳細を解説!

おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ
(読み方:おおてらの まろきはしらの つきかげを つちにふみつつ ものをこそおもえ)
作者と出典
この歌の作者は「会津八一(あいずやいち)」です。
明治から昭和初期に生きた新潟県の偉人で正岡子規とも親交があり、歌人、書家、美術史の研究家として幅広く活躍をしました。当時はまだ世間的評価の高くなかった江戸時代の僧侶で歌人の良寛に注目し、世の中に広めた人物としても知られています。自分の住まいを「秋艸堂(しゅうそうどう、秋草という意味)」と称し、号(ペンネーム)を「秋艸道人」「渾斎(こんさい)」としています。日本の歴史や美術に造詣の深い八一の歌には古寺や古仏をテーマにしたものが多くあります。
出典は「鹿鳴集(ろくめいしゅう)」です。
「鹿鳴集」は1940年に出版された会津八一の二作目の歌集です。一作目の歌集「南京新唱」の全作品とそれ以降の作品が収められています。八一は晩年に、「鹿鳴集」に自ら注釈を加えた「自註鹿鳴集」も出版しています。
おほてらの
まろきはしらの
つきかげを
つちにふみつつ
ものをこそおもへ大寺の
まろき柱の
月影を
土に踏みつつ
ものをこそ思へ「秋艸道人・鹿鳴集」で「唐招提寺にて」と載っている歌。
直筆揮毫落款入りの色紙が、わたくしのもとへ∩^ω^∩ pic.twitter.com/Izgt5yK0nI— mituakiko (@mituakiko) May 30, 2018
現代語訳と意味(解釈)
この歌を現代語に訳すと・・・
「大寺に差し込む月光が列柱を照らし濃い影を作る。その影を踏みながら私は物思いにふけるのだ。」
となります。
歌に込められた意味を余さず解釈すると、「唐招提寺の金堂に並ぶ円柱、その丸い側面を月が照らして影を作っている。私は地面に落ちたその影を踏み歩きながら、鑑真や遣唐使のことなどの遥かな歴史に思いを馳せるのだ…」となります。
文法と語の解説
- おほてら
「大寺」の意味。ここでは唐招提寺のことです。唐招提寺は奈良県にある律宗の総本山で、中国の僧である鑑真が遣唐使に招かれ来日して開いた寺です。
- まろきはしら
漢字では「円き柱」となります。唐招提寺の伽藍(寺院の中の建築物)の一つである金堂に並ぶ円柱のことです。
- つきかげ
「月影」のこと。月影は月光を指す言葉ですが、この歌では月光が柱に当たってできた影のことを言っているのだと、後に会津八一が語っています。
- つちにふみつつ
漢字では「土に踏みつつ」です。「土」は地面、「に」は助詞で、「踏み」は歩くことを指す「踏む」の連用形、「つつ」は動作が継続していることを表す接続助詞です。全体で「地面を歩きながら」という意味となります。
- ものをこそおもへ
「もの」はある物事を明示せずに漠然と示す言葉です。「もの」が何であるかははっきりとは語られていませんが、仏教に造詣の深い作者が月夜の唐招提寺で思うことは、鑑真や遣唐使のことなどでしょう。
「を」は助詞、「こそ」は係助詞です。「おもへ」は「思ふ」の已然形で、「こそ思へ」は係り結びになっており、「思うのだ…」という深い感慨を表します。
「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」の句切れと表現方法

句切れなし
この歌は深い感慨を表す係り結び「ものをこそおもへ」が第五句にあり、全体の情景も途中で変化をしないため、句切れはありません。
字余り
音数については、「ものをこそおもへ」が8音のため第五句が一字の字余りです。
結句が字余りなので「思うのだ…」という余韻がゆっくりと読み手にも伝わります。
「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」が詠まれた背景

この歌が詠まれた日、会津八一は知人と法隆寺を拝観していました。法隆寺で過ごすうちに日が暮れて、その日はうっすら月も出てきたようです。
法隆寺の伽藍にも円柱があり、夕暮れの長い影ができました。それを見て八一には思うところがあったのでしょう。「おおてらの まろきはしらの」というフレーズが浮かび、短歌にしようと呟いたと言われています。
その帰り道、八一たちは唐招提寺に寄り道をします。日もすっかり落ちた月夜、月の光が金堂に注ぎます。金堂に並ぶ円柱は青い月光を浴びて影を作りました。八一の心に先程の言葉、そして続きのフレーズも浮かびます。こうして「おおてらの」で始まる美しい歌ができあがりました。
八一は後に、何故法隆寺や唐招提寺の円柱に心惹かれたのかを次のように語っています。
自分は若い頃から東洋・西洋の歴史や美術が好きで、特にギリシャの神殿にあるような円柱の並ぶ建造物に魅力を感じていた。だからはじめに法隆寺の円柱に目を留めたのだろう。
この歌は東洋の寺院をモチーフにしながら、八一の心の中では西洋の神殿をもイメージして詠まれたのかもしれません。結びの「ものをこそおもへ」の「もの」には鑑真や遣唐使などの他に、八一が憧れたギリシャの神殿のことも含まれているのかもしれません。
「おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものをこそおもへ」の鑑賞文

この歌は、全文ひらがなで書かれており、一見分かりにくい印象かもしれません。
しかし、言葉の区切りに気がつくと、逆にそれが趣深く、味わい深く感じられます。万葉の和歌を好んだ八一らしい表現方法と言えるでしょう。
「おおてらの」という出だしは読み手を寺院へ誘います。大きな寺院です。続く「まろきはしらの」で、円柱が想像されるでしょう。古く大きな寺院の円筒形の柱がイメージされたところで「つきかげを」と来て、読み手は「ああ、これは夜の歌なのだな」と気付きます。
「月影」は通常月光を指しますが、ここでは「はしらの つきかげを」とすることで、月光が作る柱の影だと分かるようになっています。月の光が寺院を照らし陰影を作る神秘的な風景がイメージされるのではないでしょうか。
「つちにふみつつ」で柱の影が落ちた地面を歩いている作者が登場します。「歩く」ではなく「踏む」と表現することで、ただ通過するのではなくゆっくりと踏みしめているのだと想像されます。
結びの「ものをこそおもへ」は係り結びを使って作者の感慨が強調され、静かに余韻を残しています。「物思いにふけるのだ…」という作者は何を思っていたのでしょうか。それを想像する時、読み手の意識もまた月の寺院に居て「ものをこそおもへ」となっているのです。
この読後の余韻の残し方、そこに至るまでの舞台の神秘的な美しさがこの歌の魅力と言えるでしょう。
作者「会津八一」を簡単にご紹介!

(会津 八一 出典:Wikipedia)
会津八一(あいづ やいち)は、1881年(明治14年)に新潟市で生まれました。
8月1日生まれのため八一と名付けられました。文学や歴史が好きで「万葉集」などを読む子供でした。成長し東京の学校に進学すると小泉八雲や坪内逍遥の講義を受け、また新聞に載る俳句の選者もしていました。
早稲田大学を卒業した八一は新潟に帰り教師となります。その頃奈良へ旅行したのがきっかけで奈良の仏教美術に魅せられました。当時八一は俳句を多く作っていましたが、奈良旅行の後は創作を短歌へシフトし、初の歌集「南京新唱」を刊行します。
その後八一は早稲田大学の講師となり美術史を教え、仏教美術史の研究者となりました。研究のかたわら短歌も作り続け、二作目の歌集「鹿鳴集」を刊行します。
八一は晩年は故郷新潟へ帰り「夕刊ニイガタ」を創刊。新潟市名誉市民となり、1956年にこの世を去ります。生涯独身を通し妥協なく研究した八一の姿は「孤高の学者」と称されています。難しそうな印象を受けるかもしれませんが、八一の歌は神秘的で美しいものが多く、ロマンチックな一面もあったのかもしれません。奈良をこよなく愛し、何度も旅行しては美しい短歌を作りました。その歌の多くが歌碑として寺院などに残されています。
「会津八一」のそのほかの作品

- おほらかに もろてのゆびを ひらかせて おほきほとけは あまたらしたり
- わぎもこが きぬかけやなぎ みまくほり いけをめぐりぬ かささしながら
- すゐえんの あまつをとめが ころもでの ひまにもすめる あきのそらかな
- あめつちに われひとりゐて たつごとき このさびしさを きみはほほゑむ
- かすがのに おしてるつきの ほがらかに あきのゆふべと なりにけるかも












