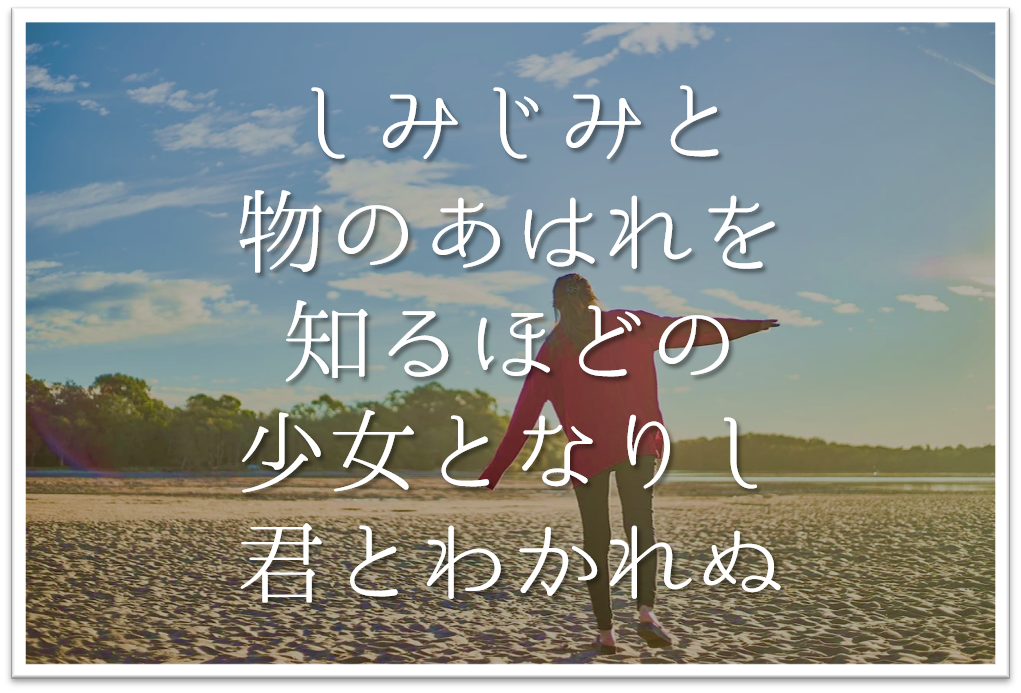
明治時代の末期から昭和10年代までを活躍した「北原白秋」。
白秋は感傷的・ロマンチシズムあふれる作風で、100年以上前の作とは思えない瑞々しい輝きを今も放ち続ける名歌の数々を詠んだ歌人です。
今回はそんな北原白秋の名歌「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」をご紹介します。
珈琲と和菓子と日本酒の店
喫茶狐菴しみじみと物のあはれを知るほどの
少女となりし君とわかれぬ優しい小雨が匂う日に。
本日も黄昏から夜更けまで、皆様のお越しを心よりお待ちしております。#狐菴 #京都 #和菓子 #日本酒 #カフェ pic.twitter.com/8LBhEDRxVB— 狐菴 KissaCo 🦊 珈琲と和菓子と日本酒の店 (@Matthew_KYOTO) April 6, 2018
本記事では、「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」の意味や表現技法・句切れについて徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」の詳細を解説!

しみじみと 物のあはれを 知るほどの 少女となりし 君とわかれぬ
(読み方:しみじみと もののあはれを しるほどの おとめとなりし きみとわかれぬ)
作者と出典
この歌の作者は、「北原白秋(きたはらはくしゅう)」です。ロマンチシズムにあふれる優しい歌を数多く詠んだ歌人です。
また、この歌の出典は大正2年(1913年)発刊、北原白秋の第一歌集『桐の花(きりのはな)』です。
この歌集には、抒情的な詩歌を発表したことで知られる雑誌『明星』の流れを汲む歌が多く収められています。この歌集が北原白秋の歌人としての地歩を固めました。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「しみじみと、物事の情趣や心の陰翳を知る少女に成長した君と、別れるのだ。」
となります。
春の愁いにふさわしい感傷的な恋の気分を詠み上げており、作者北原白秋の理想とする美の世界を表現する一首であるとも言えます。
文法と語の解説
- 「しみじみと」
「しみじみと」は副詞です。物事の様子をそれらしく表現する擬態語(オノマトペ)でもあります。擬態語については後の項で詳しく説明します。
- 「物のあはれを」
「物のあはれ」は、しみじみとした物事の情緒、無常観に裏打ちされた哀愁のことを言います。平安時代の王朝文学の時代から言われてきた、美的な観念です。
- 「知るほどの」
「知るほどの」は動詞「知る」連体形「知る」+副助詞「ほど」+格助詞「の」です。
- 「少女となりし」
「少女」は「をとめ」とフリガナがあります。「おとめ」と読みます。
「と」は格助詞です。
「なりし」は動詞「なる」の連用形「なり」+過去の助動詞「き」連体形「し」です。
- 「君と別れぬ」
「と」は格助詞です。
「別れぬ」は動詞「別る」連用形「別れ」+完了の助動詞「ぬ」終止形です。
「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、歌の中の大きな意味の切れ目のことを言います。
この歌に句切れはありませんので、「句切れなし」となります。
長いため息をつくように、別れのかなしさ、一つの恋の終わりを嘆いて切れ目なく詠まれた歌です。
擬態語(オノマトペ)
擬態語とは、直接に音響とは関係のない状態を描写するのに用いられる言葉です。「ぐんぐんと成長する」の「ぐんぐんと」、「にっこりと笑う」の「にっこりと」などがそれにあたります。
この歌には「しみじみと」という擬態語が使われています。
「物のあはれ」、物事の情趣や哀愁・繊細な心の動きや陰りといったようなものを、心の深いところで理解するさまを「しみじみと」という言葉で表現しています。
「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」が詠まれた背景

この歌の収められている歌集『桐の花』には、明治39年(1906年)から大正2年(1913年)までの歌がおさめられています。(※北原白秋が21歳から28歳の頃)
歌集『桐の花』は、「桐の花とカステラ」というエッセイが最初におかれ、「銀笛哀慕調」という章で始まります。「しみじみと…」の歌は、この章の冒頭「春」という連作の中の一首です。
エッセイ「桐の花とカステラ」は、北原白秋自身が短歌をどうとらえて詠んでいるのかについて書かれた、歌論風のものです。
このエッセイには、「悲哀」「悲しみ」「寥しさ」「哀調」といった言葉が繰り返し出てきます。北原白秋は、生きてあることへの哀しみや苦悩を語り、その感傷的情緒を短歌で表現しようとしているのです。
「しみじみと…」の歌には「もののあはれ」という言葉が出てきます。これは、本来は平安時代の王朝文学の中でいわれ始めた言葉で、しみじみとした物事の情緒、無常観に裏打ちされた哀愁のことを指します。「もののあはれ」は、白秋がエッセイ「桐の花とカステラ」で繰り返し語る「悲哀」とも通じるものがあります。
また、北原白秋はこのエッセイの中でこのようにも述べています。
「思ふままのこころを挙げてうちつけに掻き口説くよりも、私はじつと握りしめた指さきの微細な触感にやるせない片恋の思をしみじみと通はせたいのである。」
(現代語訳:熱い恋の感情の赴くままに激しく書き口説くように恋の思いを詠うよりも、私はじっと握りしめた指先でないごとかを感じ取るような繊細な感覚を大切にし、やるせない片思いの恋をしみじみと詠いたいと考えている。)
「しみじみと…」の歌こそ、繊細な感覚で詠まれた「やるせない片恋の思」であるといえます。
歌集『桐の花』のそのほかの歌
歌集『桐の花』から、「しみじみと…」を含む前後の歌をご紹介します。
銀笛のごとも哀(かな)しく単調(ひとふし)に過ぎもゆきにし夢なりしかな
(現代語訳:吹き鳴らされる銀の笛の悲しい一節のように、夢ははかなく過ぎていったことだ。)
しみじみと物のあはれを知るほどの少女(をとめ)となりし君とわかれぬ
(現代語訳:しみじみと、物事の情趣や心の陰翳を知る少女に成長した君と、別れるのだ。)
いやはてに鬱金(うこん)ざくらのかなしみのちりそめぬれば五月(さつき)はきたる
(現代語訳:春の最後に咲く鬱金ざくらが悲しげに散りはじめ、季節は五月に至るのだ。
※鬱金ざくらは、ソメイヨシノより遅れて咲く、淡い緑色の花を咲かせる桜。
葉がくれに青き果(み)を見るかなしみか花ちりし日のわが思ひ出か
(現代語訳:葉に隠れるようにして実る桜の実をみると悲しみがこみあげてくる。花が散ったあの日の思い出がよみがえるから。)
こうして連作短歌を詠んでいくと、悲しくも美しい恋物語が展開するようなドラマチックな歌が並んでいることが分かります。
「しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ」の鑑賞

「しみじみと物のあはれ…」は、青春時代のひとつの恋の終わりを素直な言葉でため息をつくように詠んだ切なくも優しい一首です。
平明な言葉で歌の言わんとするところが読み手の心にもすっと入ってくる歌であり、一度聞いたら覚えてしまえそうです。
「少女」に「もののあはれ」を教えたのは、恋だったのでしょう。
若く・幼い恋が一人の少女を成長させ、しかし二人は別れを選ぶ。この別れもまた彼女を一つ大人にさせていくのでしょう。
二人がどのように関係を育み成長し、そして別れることにしたのか、いろいろと想像したくなるようなドラマチックな雰囲気を持った抒情的な歌です。
作者「北原白秋」を簡単にご紹介!

(北原白秋 出典:Wikipedia)
北原 白秋(きたはら はくしゅう)は、福岡県生まれの詩人、歌人です。本名は北原 隆吉(きたはら りゅうきち)です。
北原白秋は、10代半ばに文学に興味をもつようになりました。与謝野鉄幹が創設し、与謝野晶子らも活躍した雑誌『明星』を好んで読みふけったといいます。明治37年(1904年)中学を退学して、早稲田大学英文科予科に入学、上京しました。早稲田大学では、同郷であることもあって、歌人の若山牧水とも親交をむすびました。雑誌『明星』を発行していた新詩社に明治39年(1906年)に参加、同じく『明星』に短歌を寄せていた石川啄木らとも知り合いました。
20代のころは、象徴主義、西洋的な思想、異国情緒あふれる趣味に親しみました。明治41年(1908年)、耽美主義的な芸術家と懇談する「パンの会」の中心メンバーとなりました。
処女歌集『桐の花』を大正2年(1902年)に発行。抒情的でロマンチシズムあふれる歌風が話題となります。
私生活においては、結婚と離婚を繰り返しました。最初の妻、松下俊子は、出会ったときにはすでに人妻であり、姦通罪で収監されるというスキャンダルを経て大正2年(1913年)に結ばれましたが、ほどなく離婚しました。(このスキャンダルの渦中の心情を生々しく伝える歌が、歌集『桐の花』の後半に収められています。)二番目の妻は詩人の江口章子で、大正5年(1916年)に結婚しましたが、大正9年(1920年)には離婚します。翌年、佐藤菊子と結婚、子供にも恵まれ、菊子とは生涯添い遂げました。
詩集、歌集を発表するのみならず、作詞家として、今でも歌い継がれる童謡の作詞をしました。
昭和17年(1942年)糖尿病と腎臓病が悪化して逝去。享年57歳でした。
「北原白秋」のそのほかの作品

(北原白秋生家 出典:Wikipedia)
- 君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ
- 春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕
- ヒヤシンス薄紫に咲きにけりはじめて心顫ひそめし日
- 廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける
- 手にとれば桐の反射の薄青き新聞紙こそ泣かまほしけれ
- 草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり
- ひいやりと剃刀ひとつ落ちてあり鶏頭の花黄なる初秋












