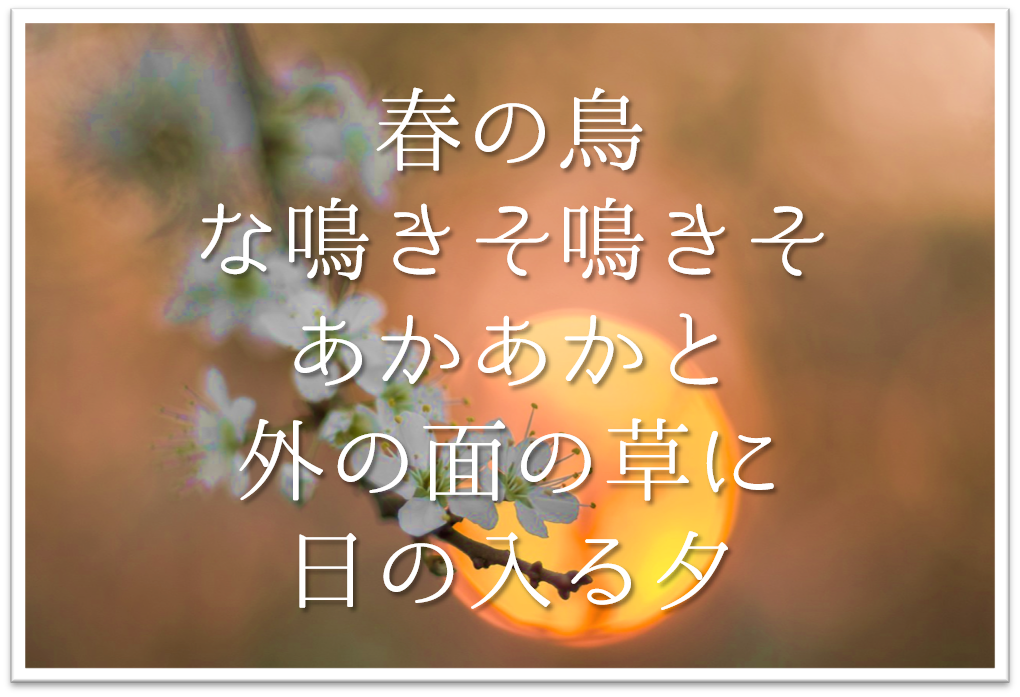
万葉の時代より親しまれてきた日本の伝統文学のひとつである「短歌」。五・七・五・七・七の調べで、日本の美しい自然や繊細な歌人の心の内を歌い上げます。
現代まで多くの歌人が優れた歌を残してきましたが、その中でも日本の近代文学に偉大な足跡を残した詩聖・北原白秋がいます。
今回は、白秋の代表歌「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」をご紹介します。
春の鳥 な鳴きそ鳴きそ あかあかと
外の面の草に 日の入る夕
_____桐の花 pic.twitter.com/alMVcX635H— 葵みりあ☻ (@_2525today) April 7, 2017
本記事では、「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」の詳細を解説!

春の鳥 な鳴きそ鳴きそ あかあかと 外の面の草に 日の入る夕
(読み方:はるのとり ななきそなきそ あかあかと とのものくさに ひのいるゆうべ)
作者と出典
この歌の作者は、「北原白秋(きたはらはくしゅう)」です。
白秋は明治期から昭和時代前期にかけて活躍した詩人・歌人です。
「明星」の歌人として出発し、耽美主義運動を実施。異国情緒・官能性豊かな象徴的詩風でしたが、後に自然賛美の作風に転換していきます。短歌・同様・民謡でも独自の境地を開拓し、数々の名作を世に送り出しました。
また、この歌の出典は第一歌集『桐の花』です。春夏秋冬の四季立てで構成された歌集で、この歌は「春」の巻頭を飾っています。
現代語訳と意味(解釈)
この歌を現代語訳すると・・・
「春の鳥よ、そんなに鳴かないでおくれ。外の草原を赤々と染めながら夕日が沈もうとしている。」
という意味になります。
教科書にも取り上げられている白秋を代表とする歌なので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?春の夕暮れという物悲しさの中で鳥の鳴き声にいっそう寂しさが募る、青年の感受性豊かな心を詠んだ歌です。
文法と語の解説
- 「な鳴きそ鳴きそ」
「な~そ」は古文ではよく使われている禁止を表す助詞で、「~しないでくれ」という意味になります。二度繰り返しており、二回目の「な」は省略してあります。
この歌では、春の鳥に向かって「鳴くな、鳴いてくれるな」と呼びかけている様子を表しています。あえて古典表現を用いたことで、白秋が意識して「万葉調」を取り入れていることがわかります。
- 「あかあかと」
赤く染め上げる夕日を哀調溢れる旋律で表現しています。これは当時有名であった、斉藤茂吉の『赤光』『あらたま』で多用したフレーズに影響を受けたものと考えられています。
- 「外の面」
「とのも」と読み、戸外や屋外を意味します。
「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、意味や内容、調子の切れ目を指します。歌の中で、感動の中心を表す助動詞や助詞(かな、けり等)があるところ、句点「。」が入るところに注目すると句切れが見つかります。
この歌の場合は二句目の「な鳴きそ鳴きそ」で一旦歌の流れが句切れますので、「二句切れ」となります。
この句切りを境に鳥の鳴き声から目の前の光景に展開していき、聴覚と視覚に訴える表現で春の黄昏時を描写しています。
体言止め
体言止めとは、文末を助詞や助動詞ではなく、体言(名詞・代名詞)で結ぶ表現方法です。文を断ち切ることで言葉が強調され、「余韻・余情を持たせる」「リズム感をつける」効果があります。
この歌も「日の入る夕」と名詞で結んでおり、沈んでいく夕日の寂しげな様子を、余韻を残して歌い上げています。
同音同語の反復表現
同じ音や言葉を繰り返して使う言葉のことで、意味を強めたり、事物の複数を示したり、動作や作用の反復・継続などを表したりします。一首の中で、言葉を繰り返し用いる表現は、短歌でもよく用いられる技法です。
三十一文字の中で同じ言葉を使うため、伝えられる情報量が少なくなりますが、感情の高ぶりや思いを強調し、リズムにメリハリが生まれるといった効果があります。
この歌では、「鳴きそ鳴きそ」「あかあか」に反復表現が用いられており、心地よいリズムを生み出しています。
また、単に同じ言葉を繰り返すだけでなく、この二つには共通点がありどちらも「あ行+か行」の音韻で続いていることに注目します。
「な鳴きそ鳴きそ」の句切れで文が一旦句切られていますが、「あ行+か行」の連続性により、一首の統一性を高めています。
「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」が詠まれた背景と鑑賞

この歌は1907年7月、森鴎外の家で開かれた歌会「観潮桜歌会」に招かれて詠んだ歌です。
鴎外は1907年から1910年までの間毎月歌会を開いているのですが、この会の目的として「明星」と「アララギ」の二つを接近させ国風新興を夢見たと述べています。
明星派であった白秋も、「観潮桜歌会」をきっかけに斉藤茂吉やアララギ派の歌人とも面識を得るようになりました。
この頃、白秋は早稲田大学在学中22歳で、新進歌人として最も気鋭の時でした。こうした文学的な交流は白秋の作品にも大きな影響を与えたといわれています。
またこの歌が詠まれた1907年とは、日露戦争を経験して間もない年です。
春といえば誰もが心弾む季節のように感じますが、当時は春の喜びをのびやかに歌う心情ではなかったのかもしれません。
未来への漠然とした不安や悲しみを象徴するように、この歌にも暗い影を投げかけています。
「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕」の鑑賞

春の鳥の明るいさえずりよりも、あかあかと不安をあおるような夕暮れ時の物寂しい情景を詠んだこの歌は、多感な青年時代の真っ只中にいる白秋の心情を如実に表現しています。
青春の愁いを聴覚と視覚を巧みに取り入れ、叙情豊かに歌い上げた作品です。
春の夕暮れ時という、憂いに満ちた時が流れる一日の終わりの風景を、部屋の中から眺めている一人の青年。胸に迫る光景を前に、「小鳥よ、鳴かないでおくれ、これ以上私の心を沈ませないでほしい」と語りかけています。
しかし、この歌の具体的な情景を思い浮かべようと試みても、像がぼやけてしまうのではないでしょうか。春の鳥とはどんな鳥であったのか…。
「鳴いてくれるな」と懇願しているのは、今まさに目の前の風景に呼応するように鳴いているのでしょうか。それとも夕日がゆっくりと沈んでいく静寂にしばし浸っていたいから、このまま鳴かないでいてくれということなのか。
想像すればするほどわからなくなってしまうかもしれません。
情景については様々な解釈がなされていますが、この歌が収められている歌集『桐の花』の序文「桐の花とカステラ」で、白秋はただ「春の夕暮れの雰囲気、それさえ感じ取ってくれればよい」ということを述べています。
視覚や聴覚といった五感を駆使して、「春の夕暮れの雰囲気」を三十一文字に凝縮する卓越した白秋の技法が感じられる歌です。
作者「北原白秋」を簡単にご紹介!

(北原白秋 出典:Wikipedia)
北原白秋(1885~1942)は、本名は北原 隆吉(きたはら りゅうきち)といい、熊本県玉名郡の海産物問屋の長男として生まれました。中学時代より学業の傍らに詩作に励み、明星派へ傾倒していきます。
1904年に早稲田大学英文科へ入学後、同級生の若山牧水と中林蘇水らと交流を深めていきます。この頃、号を「射水(しゃすい)」と称していたことから、彼ら三人を「早稲田の三水」と呼ばれていました。
明星脱退後、1908年に木下杢太郎らと「パンの会」を結成し、耽美主義運動を推進します。1909年には象徴詩に新しい風をふきこんだ『邪宗門』を、19011年に少年の日の哀歓をうたった『思ひ出』の二冊の詩集を出版。文壇の地位を確立し多方面に才能が認められていきました。
私生活では、松下俊子とのスキャンダルや生家の破産により深刻な精神的ダメージを受けますが、その後も『桐の花』『東京景物詩』など精力的に歌を発表しています。
次第に華麗な作風から自然賛美なものに転換し、童謡・民謡などの様々な分野でも名作を残しました。
晩年は眼の酷使と糖尿病・腎臓病の合併症で、ほとんどの視力を失いながらもさらに歌作に没頭していきます。1942年病床でも執筆や編集を続けましたが、「ああ素晴らしい」の言葉を残して自宅で亡くなりました。57年の生涯において、最期まで創作意欲が衰えることはありませんでした。
「北原白秋」のそのほかの作品

(北原白秋生家 出典:Wikipedia)
- 君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ
- 春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕
- ヒヤシンス薄紫に咲きにけりはじめて心顫ひそめし日
- 廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける
- 手にとれば桐の反射の薄青き新聞紙こそ泣かまほしけれ
- 草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり
- ひいやりと剃刀ひとつ落ちてあり鶏頭の花黄なる初秋












