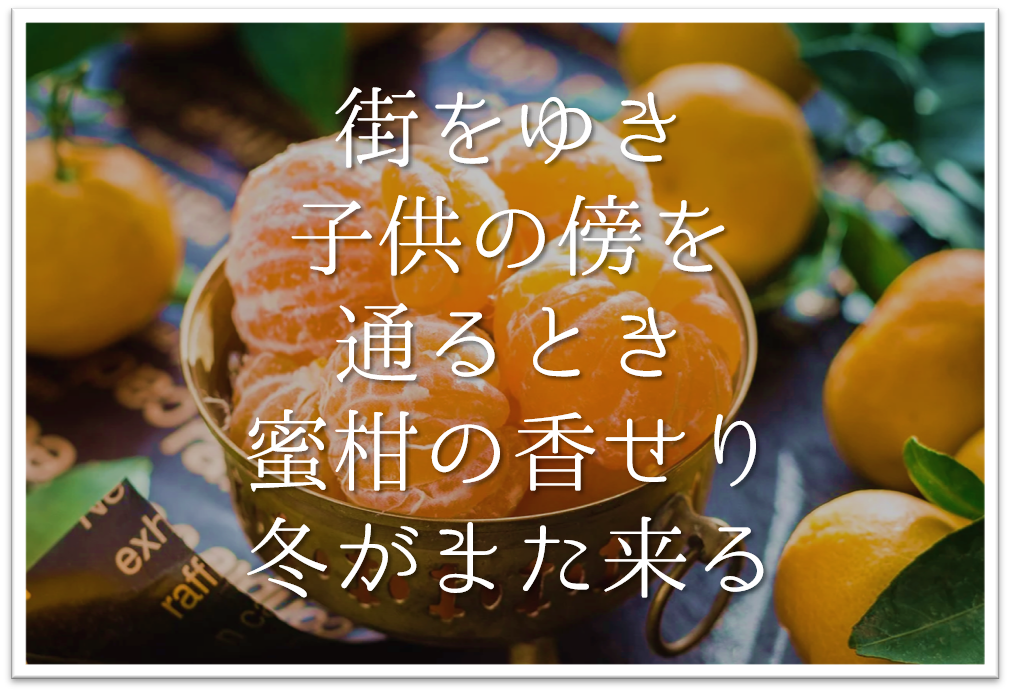
万葉の時代より親しまれてきた日本の伝統文学のひとつに短歌があります。
五・七・五・七・七の調べにのせて、歌人の心情を描く叙情的な作品が数多く残されています。
今回は、冬の訪れを香りで表現した歌「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」をご紹介します。
『街をゆき 子供の傍を 通る時 蜜柑の香せり 冬がまた来る』か。 pic.twitter.com/BqAcfGC4Ps
— Takayoshi Fujii (@Norwich_Taka) October 28, 2018
本記事では、「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」の詳細を解説!

街をゆき 子供の傍を 通る時 蜜柑の香せり 冬がまた来る
(読み方:まちをゆき こどものそばを とおる時 みかんのかせり ふゆがまたくる)
作者と出典
この歌の作者は、「木下利玄(きのしたりげん)」です。木下氏は明治末期から大正にかけて活躍した歌人です。白樺派の歌人として写実的に独自の歌風を確立。口語や俗語を駆使した写実的な短歌は、「利玄調」と呼ばれています。
また、この歌の出典は大正8年(1919年)に刊行された第二歌集『紅玉』です。
現代語訳と意味(解釈)
この歌を現代語訳すると・・・
「町を歩いていて子供とすれ違った時、ほのかに蜜柑の香りがした。ああ、また冬がやって来るのだなあ。」
という意味になります。
前から歩いてきた子供は、少し前に甘酸っぱい蜜柑を食べたのでしょうか。漂ってきた残り香から、冬の訪れを感じています。ふいに気付かされた季節の移ろいに、感慨に浸る作者の心情が伝わってくる一首です。
文法と語の解説
- 「香せり(かせり)」
「香」+動詞の「す」の未然形「せ」+完了の助動詞「り」の形式で、「香がした」と訳します。
「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、意味や内容、調子の切れ目を指します。歌の中で、感動の中心を表す助動詞や助詞(かな、けり等)があるところ、句点「。」が入るところに注目すると句切れが見つかります。
この歌の場合は、「香りせり」で一旦歌の流れが止められており、句点「。」を打つことができますので、「四句切れ」となります。
四句目までは、子供がそばを通り過ぎた時にみかんの香りが漂ってきたことを伝え、五句目で冬の訪れを感じ取ったことを表現しています。
文語と口語を織り交ぜた表現
この歌には、文語と口語が混在しています。
「みかんの香せり」までが文語で詠まれていますが、「冬がまた来る」と最後はあえて口語に転換しているのです。
「冬また来る」というように一貫して文語で表現するよりも、口語を織り交ぜることで新しいリズムを生み出すことに成功しています。
このように文語の中に大胆に口語を取り入れる巧みな表現方法は、利玄の得意とするものでした。
「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」が詠まれた背景

この歌は、大正4年(1915年)の利玄が30歳の時に詠んだ作品です。雑誌『白樺』の一月号に発表され、後に歌集『紅玉』にも収録されました。
歌集では、 「子供ゐてみかんの香せり駄菓子屋の午後日のあたらぬ店の静けさ」 という歌とともに載せられています。
蜜柑という果物は、明治末期から大正時代にかけて栽培技術が向上し、庶民の生活でも普及するようになります。食べやすく甘酸っぱい味わいは、とりわけ子ども達の好物でもありました。その為、冬が近づき始めるころ店先に並んだ蜜柑に子ども達は飛びついたといいます。
利玄は上記のように子供を題材とした歌を多く残しています。しかし、この歌を詠んだ頃利玄は、生後いくほどもなく我が子を失っているのです。
元気に駆け回る子ども達への優しい眼差しを感じる一方、利玄の深い悲しみを想起させる歌にも感じられます。
「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」の鑑賞

この歌は、蜜柑が持つ晩秋の季節感を香りでとらえた歌です。
蜜柑を食べたあとはその香りが強く残るものですが、大人ではなく子供から漂ってきたところから、ノスタルジアにも似た心象を感じます。
その新鮮な香りに、もう秋が終わるのかと過ぎ行く季節を見つめ、言いようのない感慨に浸っています。そしてふたたびやって来る長い冬への思いが込められている歌です。
「蜜柑の香せり」という文語から「冬がまた来る」という口語によって大胆に表現したことで、庶民的な親しみやすさを感じます。
さらに、一句「ゆき」・三句「時」・四句「せり」とイ段の音で終わらせることで、歯切れ良く快活なリズムを生んでいます。
それによって街中を元気に駆け回る子ども達の様子を連想させています。国語的発想を駆使した利玄らしさがよく表れた短歌です。
作者「木下利玄」を簡単にご紹介!

(木下利玄 出典:Wikipedia)
木下利玄(1886~1925)は岡山県の生まれで、利玄は本名「としはる」と読みます。
伯父・木下利恭の死去により、5歳で木下子爵家の養子となり上京しました。親元から引き離され、前当主夫人もすでに亡くなっていたため、乳母もつけられず孤独な幼少期を送っています。
中等科時代から作歌を志し、13歳で佐々木信綱に師事し短歌を学びます。「心の花」の有力な同人として活躍しました。
1910年には、志賀直哉・武者小路実篤らとともに、文芸雑誌『白樺』を創刊します。初期には小説も書いていましたが、のちに短歌に専念しました。当初は北原白秋・島木赤彦の影響を受け感覚的な歌を発表していましたが、しだいに人間味あふれる歌を詠んでいます。
四四調と呼ばれる独特のリズムを取り入れ、口語を使用した平易で写実的な短歌は「利玄調」と呼ばれ、歌壇に新風を巻き起こしました。
歌集に『紅玉』のほかに『銀』などがありますが、中でも1924年に発行した『一路』は大正期の歌壇で高い評価を得ています。
私生活では1911年に妻を迎え、三人の子供にも恵まれています。しかしいずれも幼くして亡くしており、己の無力さと現実の残酷さに耐え続けなければなりませんでした。
それでも歌を詠むことをやめなかった利玄は、ますます作歌活動に全力を注ぎました。しかし1922年には肺結核にかかり、病床の身となってから4年後39歳という若さでこの世を去っています。
『木下利玄』のそのほかの作品

(木下利玄歌碑 出典:Wikipedia)
- 牡丹花は咲き定まりて静かなり花の占めたる位置のたしかさ
- 大き波たふれんとしてかたむける躊躇(ためらひ)の間(ま)もひた寄りによる
- 遠足の小学生徒有頂天に大手ふりふり往来とほる
- 曼珠沙華一むら燃えて秋陽(あきび)つよしそこ過ぎてゐるしづかなる径(みち)
- 亡き吾子の帽子のうらの汚れみてその夭死(はやじに)をいたいけにおぼゆ












