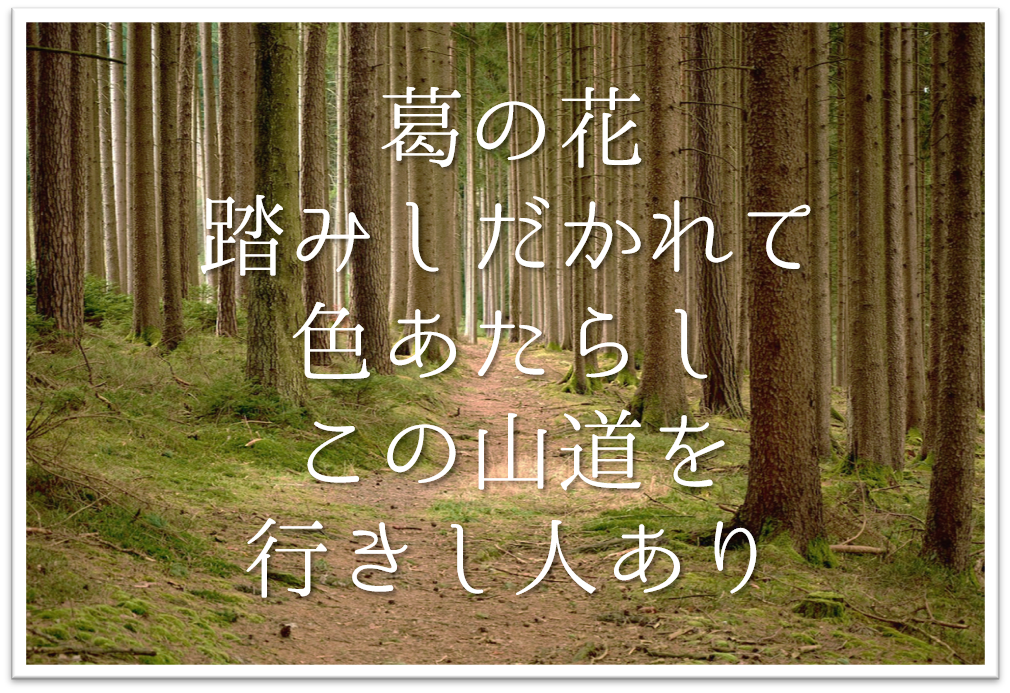
近現代においては、短歌のモチーフとしてたびたび取り上げられている葛の花。都会に住んでいると葛の花がどんな花なのか知らない人の方が多いでしょう。葛の根っこから作られる葛粉は、真っ白で清浄なイメージです。くずきりやくず餅の原料として有名ですね。
葛の花も白い花なのでは?と思われがちですが、葛の花は、色鮮やかな赤紫。鮮烈でなまめかしい印象を与える花です。
そんな葛の花を初めて短歌のモチーフとして取り上げた歌人が釈迢空です。
今回は、葛の花を詠った歌人として、現代でも人気の高い釈迢空(折口信夫)の歌「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」をご紹介します。
『葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり』
釈迢空
葛の花。。。 pic.twitter.com/MJiRdeYyV5— 午後3爺 (@gogo3jih) August 28, 2013
本記事では、「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「葛の花踏みしだかれて色あたらしこの山道を行きし人あり」の詳細を解説!

葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり
(読み方:くずのはな ふみしだかれて いろあたらし このやまみちを ゆきしひとあり)
作者と出典
この歌の作者は「釈 迢空(しゃく ちょうくう)」です。歌人・釈迢空は、大阪生まれの国文学者で民俗学者として有名な人物で、学者としては折口信夫の名前で活動していました。
この歌の出典は『海やまのあひだ』です。
大正14年 (1925年) 刊行。この歌は大正13年 (1924年) に詠まれた歌です。連作「大正十三年 -五十二首- 島山」の冒頭にある、非常に有名な歌です。
現代語訳と意味 (解釈)
この歌を現代語訳すると・・・
「あざやかな赤紫の葛の花が 踏みにじられて、鮮烈な色があたり一面に広がっている。ああ、この山道を自分より先に通った人がいるのだ」
という意味になります。
人気のない山道をたったひとりで歩いていた釈迢空。ここまで歩いて、誰とすれ違うこともありませんでした。そこで見つけた、踏みにじられたあざやかな葛の花。ぐちゃぐちゃに踏まれて広がる赤紫の色彩と、甘酸っぱい匂いに触れたときの感動を、写実的に詠んだ歌です。
文法と語の解説
- 「葛の花」
葛は豆科の草です。晩夏に短い藤の花房を立てたような赤紫の花をつけます。
『万葉集』で山上憶良が秋の七草の一つにあげた葛(くず)。
美しい紫色が8月の空を背景に心を和ませてくれます。
根の部分は葛根として風邪薬に使われます。花には肝機能を整える効果があります。花言葉は「活力、治癒」。
「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」釈迢空 pic.twitter.com/4oFOPTPV0q
— 白笹稲荷神社 公式 (@Shirasasa_Inari) August 19, 2019
- 「しだかれて」
「荒れる」「乱れる」という意味です。
- 「あたらし」
「新し」「新鮮だ」という意味です。
「葛の花踏みしだかれて色あたらしこの山道を行きし人あり」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、一首の中での大きな意味上の切れ目のことで、読むときもここで間をとると良いとされています。
この歌は「色あたらし。」のところで一旦文章の意味が切れます。三句目で切れていますので、「三句切れ」の歌となります。
句読点の使用
この歌の大きな特徴は句読点が使用されているという点にあります。特に句点はこの歌を鑑賞するにあたり、大きな意味を持ちます。
「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」
「色あたらし。」と三句目に句点があり、「行きし人あり」と結句に句点がありません。
これは作者の感動の中心は「葛の花の色のあざやかさ」にあり、「山道を通った人がいる」ことに比重を置いていないということを意味しています。
「葛の花踏みしだかれて色あたらしこの山道を行きし人あり」が詠まれた背景

この歌は、沖縄での民族調査の帰途、調査のため訪れた壱岐の山中で生まれた歌だと言われています。
壱岐は九州・福岡の玄界灘に浮かぶ、自然に恵まれた美しい島です。現在でも、集落以外で人とあまり出会うことのない人口の少ない島です。
釈迢空がひとりで山道を歩いていたときも、誰とすれ違うこともありませんでした。人気が感じられない荒々しい山道であったことが想像できます。
この歌が詠まれた季節は定かではありませんが、葛の花が晩夏に咲く花であることから、8月中旬から9月にかけて詠まれた歌なのではないかと思われます。
「葛の花踏みしだかれて色あたらしこの山道を行きし人あり」の鑑賞

「山道を這うように咲いている葛の花が踏みつぶされている」。
人が多い山であればごく当たり前の光景ですが、作者が歩いていたのは、誰とも出会うはずがない、人気のない壱岐の山道です。そのため、人の痕跡があった「踏みにじられて葛の花の赤紫があたり一面に広がっている」ことに作者は感動しています。
この歌は、読む人によってさまざまな解釈が可能な歌です。作者・釈迢空 (折口信夫) 自身がこの歌について解説していますので、ご紹介します。
「壱岐は島でありながら、伝説の上では神代の一国である。それだけに海としても個性があり、山としても自ら山として整うた景色が見られた。蜑の村に対して、これは陸地・耕地・丘陵の側を眺めたものが集まつてゐる。山道を歩いてゐると、勿論人には行き逢はない。併し、さういふ道に、短い藤の花房ともいふべき葛の花が土の上に落ちて、其が偶然踏みにじられてゐる。其色の紫の、新しい感覚、ついさつき、此山道を通つて行つた人があるのだ、とさういふ考へが心に来た。」
『折口信夫全集 31(自歌自註・短歌啓蒙 歌評)』(折口信夫[著])(1997年刊行) より
この文章から、作者が壱岐の山の美しさに触れ、素直に感動している様子が見てとれます。とりわけ、踏みにじられた葛の花が作者の琴線に触れたのではないでしょうか。
また、これと別の釈迢空 (折口信夫) 作品集にも、この歌についての作者による解説が収められていますのでご紹介します。
「もとより此歌は、葛の花が踏みしだかれてゐたことを原因として、山道を行つた人を推理してゐる訣(わけ)ではない。人間の思考は、自ら因果関係を推測するやうな表現をとる場合も多いが、それは多くの場合のやうに、推理的に取り扱ふべきものではない。これは、紫の葛の花が道に踏まれて、色を土や岩などににじましてゐる処を歌つたので、……この色あたらしの判然たる切れ目が、今言つた論理的な感覚を起し易いのである。」
『日本近代文学大系・折口信夫集』(1972年刊行) より
釈迢空は、「葛の花が踏みしだかれているのは、山道を行った人があるからだ」という、推理的な受け取り方を危ぶんでいます。
この歌についてはあれこれ裏の意味を想像するよりも、作者の解説通り、作者がその目で葛の花を見たときの新鮮な感覚、心の動きを素直に受け止めるのが、正しい鑑賞法だと言えそうです。
歌にしようと思うほど釈迢空の心をとらえた葛の花は、どんな花なのでしょうか?
豆科の草である葛の花は、晩夏に藤の花房を立てたような赤紫の花をつける、とても生命力が強く美しい花です。
人が歩く道にまで咲き乱れるたくましい花。その赤紫の色はあざやかですがほの暗く、形も少し変わっているというか、数が多ければやや不気味な感じもするでしょう。甘酸っぱい匂いを放つ葛の花には、その匂いに引き寄せられて、多くの虫が集まってきます。踏みにじられた葛の花は、さらに匂いたち、あたり一面を赤紫に染めたのでしょう。
作者「釈迢空」を簡単にご紹介!

(釈迢空"折口信夫" 出典:Wikipedia)
歌人・釈迢空 (しゃく ちょうくう)は、日本の民俗学者、国文学者、国語学者として知られている折口信夫 (おりくち しのぶ) と同一人物です。
柳田國男の高弟として、民俗学の基礎を築きました。歌人としては、「アララギ」に参加して活躍、後に古泉千樫らとともに反アララギ派を結成して歌誌『日光』を創刊しました。
釈迢空 (本名:折口信夫) は、明治20年 (1887年)、大阪府西成郡木津村の父秀太郎 (医師)、母こうの四男として生まれました。
初めて短歌を詠んだのは7歳のときだと言われています。15歳のときには歌誌に投稿した短歌が入選を果たします。中学校卒業後、医学を学ばせようとする家族の勧めに従って第三高等学校を受験しようとしますが、直前に進路を変更し、國學院大學国文科に進みます。ここで国学者三矢重松に教えを受け、強い影響を受けました。
短歌に興味を持ったのも大学時代です。卒業後は、中学の教員として働きながら民俗学の研究に励み「三郷巷談」を柳田國男主催の『郷土研究』に発表し、以後、柳田の知遇を得ます。
民俗学者として精力的に活動する中、歌人としては大正14年 (1925年) に処女歌集『海やまのあひだ』を刊行し、高い評価を得ました。
1953年9月3日 #折口信夫 逝去。日本の民俗学の嚆矢であった柳田国男に師事し、これを独自に体系化した。世にいう「折口学」は民俗学に留まらず、国文学、文化論などにも影響を及ぼしている。
また歌人として、釈迢空と号した。代表歌は、葛の花 踏みしだかれて 色あたらし。この山道を行きし人あり pic.twitter.com/u4EQQO9Mwm
— 酒上小琴【サケノウエノコゴト】 (@raizou5th) September 2, 2018
「釈迢空」のそのほかの作品

(「折口信夫生誕の地」の碑 出典:Wikipedia)
- 道なかに人かへりみずたちつくす道祖神とわれとさびしと言はむ
- 櫻の花ちりぢりにしもわかれ行く遠きひとりと君もなりなむ
- いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみをもぎはなちたり
- 水底に、うつそみの面わ沈透(シヅ)き見ゆ。來む世も、我の寂しくあらむ












