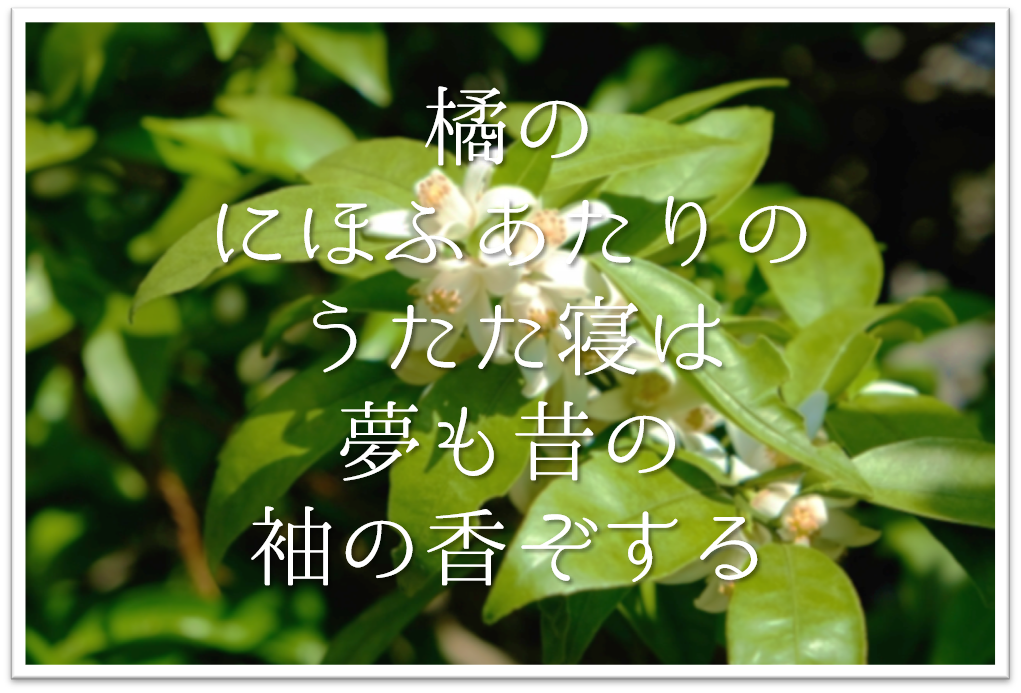
万葉の時代より連綿と続く短歌の世界。五・七・五・七・七の三十一文字で表現した短歌には、歌人の心情を描く叙情的な作品が多くあります。
中でも恋心を題材にした歌は、古来の歌集でもたびたび詠まれてきました。
今回は『新古今和歌集』の中から、昔の恋を艶やかに歌い上げた「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」について紹介します。
橘の匂ふあたりのうたた寝は
夢も昔の袖の香ぞする
俊成卿女
彼女の歌の中でもかなり好きな歌。
夕方のこんな時間の、橘の香る庭の匂いが好き。暖かくて甘くて。 pic.twitter.com/3fVFsI2dEG— mika n (@mikanegishi) May 5, 2019
本記事では、「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」の詳細を解説!

(ヤマトタチバナの花 出典:Wikipedia)
橘の にほふあたりの うたた寝は 夢も昔の 袖の香ぞする
(読み方:たちばなの におうあたりの うたたねは ゆめもむかしの そでのかぞする)
作者と出典
この歌の作者は、鎌倉時代前期の女流歌人「藤原俊成女(ふじわらのしゅんぜいのむすめ/としなりのむすめ)」です。後鳥羽院に出仕し、「皇太后宮大夫俊成女」「俊成卿女」の名で歌壇で活躍しました。
(※皇太后宮大夫とは、皇太后宮殿の長官のことで俊成の最終官位のことです。)
この歌の出典は、鎌倉時代に編纂された勅撰和歌集『新古今和歌集』(夏・245)です。
俊成女はこの歌のほか、28首もの歌が入集し、当時から高い評価を得ていたことが窺えます。
現代語訳と意味(解釈)
この歌を現代語訳すると・・・
「橘の花の香が薫るあたりでうたた寝をしていると、夢の中でも昔親しかった人の袖の香がすることです」
という意味になります。
「橘」とはミカン科の常緑小高木のことで、夏の古歌に詠まれる代表的な景物です。5月~6月ごろに純白色の小さな花を木いっぱいに咲かせ、爽やかな香りを放ちます。
この橘の香りを和歌の世界では、懐旧の情を起こさせるもの、特に「昔の恋人への心情を思い出させるもの」として定着していました。
また「袖の香」とは、袖に焚きしめていた香りのことです。現代のように毎日入浴することが難しい時代、貴族達は男性も女性も着物にお香を焚き染めていました。平安時代には、「梅花香」など花の香に似た香が好まれており、花橘の香に擬したものもあったのでしょう。
つまり、昔の恋人が焚いていた薫物が橘の香であったため、橘の花の香りがたちこめるあたりでうたた寝をしていたら、昔の恋人が夢に現れたと解釈できます。
懐旧の情の象徴であった橘の香りをきっかけに、昔の恋が甦った情感を艶やかに歌い上げています。
文法と語の解説
- 「にほふ」
「匂ふ(にほふ)」の連体形で、「香りが漂う」様子を表しています。他にも「美しく咲いている、美しく映える」「恩を受ける」といった意味もあります。
- 「うたたね」
うとうとと眠ること、浅く眠ることを意味します。和歌では恋のイメージを漂わせる言葉としても使われます。
- 「香ぞする」
「ぞ~する」で係り結びの形をとっており、「ぞ」+文末の語が連体形で強調を表します。この歌も「する」という「す」の連体形になっています。現代語訳にするときは特に訳す必要はありません。
「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」の句切れと表現技法

句切れ
この歌に句切れはありませんので、「句切れなし」となります。
夢とうつつの境をぼやかすように、途切れることなく詠みあげられた一首です。
本歌取り
本歌取りとは、一首の中に有名な古歌(これを本歌といいます)の語句を取り入れて詠む、和歌の作成技法のひとつです。本歌を背景として、余情を豊かにする効果があります。
特に平安時代末期、藤原俊成の頃から意識的に取り入れられ、新古今時代に盛んに行われました。藤原俊成女の歌は、本歌取りの技法を駆使した技巧的で妖艶な作品が特徴です。
この歌も『古今和歌集』にある以下の一首を本歌として、本歌取りの技法が用いられています。
五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする(読み人知らず)
(現代語訳:五月を待って咲く橘の花の香をかぐと、昔親しくしていた人の袖の香りが薫ってくるものだ。)
『古今和歌集』は当時の一般教養として親しんでいたものなので、この歌も読み手には本歌が何であるかはすぐに理解できたことでしょう。「橘のにほふ」「昔の袖の香り」で本歌の背景を連想させ、表現効果の重層化に成功しています。
本歌の「花橘の香をかげば」というややストレートな表現を「橘のにほふあたりのうたた寝」と抽象的に表すことで、より詩的な趣きが感じられます。
また、付け加えると『新古今和歌集』には他にも「花橘」を本歌とする歌が多く詠まれています。
- 【誰かまた 花橘に 思ひ出でん 我も昔の 人となりなば】(藤原俊成)
- 【五月闇 短き夜半の うたたねに 花橘の 袖に涼しき】(慈円) など
いかに「花橘」の歌が愛されていたかがわかりますね。
「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」が詠まれた背景

この歌が詠まれた新古今の時代には、橘の香りは昔の恋人への心情を象徴するものでした。橘の花は、旧暦五月の忌み月(男女交渉が禁じられていた)を待って咲くので、恋の切なさがよりいっそう感じられたことでしょう。
当時、女性は特定の人にしか顔を見せることができませんでした。高貴な貴族達は、男女の会話もいつも御簾ごしが基本で、視覚情報が限られていました。そんな時代だからこそ、人と香りの関係は現代以上に強いものであったのでしょう。爽やかな花橘の香りをきっかけに、過ぎ去った恋の記憶が描かれています。
そして昔の親しかった人が夢に出てくるということは、相手が自分のことを想っているからだと考えられていました。すでに関係は途絶えてしまったはずの恋人が、なぜか自分の夢に出てきたということに戸惑ったかもしれません。
しかし、まだ相手の袖の香を覚えていたということから、ただの感傷や懐旧の情念だけでなく、自分のなかにかすかに残っていた恋人への愛情のようなものが感じられます。
今はもう叶わない恋も、花橘の時期に見る夢の中では、かつての恋人と永遠の逢瀬が遂げられたのかもしれません。
「橘のにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする」の鑑賞

この歌は、女性らしいきめ細やかな抒情のなかに恋の切なさや、妖艶な情感を醸し出しています。
夏のある日、眠りに落ちる心地よさの中、もう忘れていたはずの昔の恋人が、白昼夢のような幻想的な世界でゆらゆらと現れます。ふと目覚めたときも、夢と同じようにあの人が袖に漂わせていた花橘の香りがほのかに漂っているのでした。
「あぁ・・・夢を見ていたのね・・・」と、橘の花をぼんやりと物憂げに眺める女性の姿が浮かびます。
あたりを漂う花橘の香りに揺さぶられる感情を、わずか三十一音で作者の心象風景を伝えています。まさに新古今和歌風のお手本のような歌といえるでしょう。
本歌では花橘に昔慣れ親しんだ人を想うだけですが、この歌ではうたた寝に見る夢の中でも恋人の袖の香りがすると表現しています。
過去の恋を現実と夢の二重に懐旧し、深い喪失感をたたえた味わい深さが増しています。
作者「藤原俊成女」を簡単にご紹介!

(皇太后宮大夫俊成女 出典:Wikipedia)
藤原俊成女(1171年~1251年)は、鎌倉時代前期に活躍した女流歌人です。新三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人に称されました。
尾張守藤原盛頼と八条院三条(藤原俊成の娘)の間に生まれましたが、1177年に、父・盛頼が鹿ケ谷の陰謀の首謀者の一人として失脚、八条院三条とは離婚しています。
以後は、母方の祖父である藤原俊成のもとに預けられ、娘として養育されました。藤原俊成といえば、『新古今和歌集』の選者でもある藤原定家の父でもあり、第一級歌人として活躍しています。
1190年頃に源通具と結婚し、一男一女を儲けます。しかし1199年頃、夫・通具が当事権勢の中心に居た女房・従三位按察局(土御門天皇の乳母)を新しく妻に迎えてから、結婚生活は決して幸せなものではありませんでした。
行き場を失った俊成女でしたが、30歳を過ぎてから後鳥羽院に歌の才能を見出され、1202年に女房として御所に出仕します。
幼い頃から俊成に磨かれただけに、目覚しい活躍を遂げる俊成女は、『新古今和歌集』以降の勅撰集、歌合等に多数の作品を残しました。1213年に出家した後も歌壇での活躍は続きますが、1241年藤原定家の没後は、播磨国越部庄に下り余生を過ごしました。












