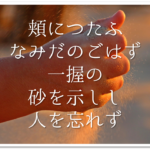五・七・五・七・七の三十一文字で詠まれる「短歌」。
自ら短歌を作ることはなくとも、美しい歌を鑑賞し、折にふれて嚙みしめているという人も多いでしょう。優れた歌は文学性も高く、多くの人の共感をよんでいます。
抒情性の高い望郷の歌や、青春時代の繊細な歌で知られる歌人に明治時代に活躍した石川啄木がいます。
今回は、そんな石川啄木の短歌の中から、「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」という歌をご紹介します。
いのちなき
砂のかなしさよ
さらさらと
握れば指の
あひだより落つ(石川啄木)#海 #追憶 pic.twitter.com/Mk4gFg1dkk
— 綾野b (@erenbkuchiku1) April 3, 2019
本記事では、「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」の詳細を解説!

いのちなき 砂のかなしさよ さらさらと 握れば指の あひだより落つ
(読み方:いのちなき すなのかなしさよ さらさらと にぎればゆびの あいだよりおつ)
作者と出典
この歌の作者は「石川啄木(いしかわたくぼく)」です。
明治時代の歌人で、『一握の砂』、『悲しき玩具』といった歌集が刊行されています。
この歌の出典は、明治43年(1910年)12月に刊行された石川啄木の第一歌集『一握の砂』です。
(※前書きによると、この歌集には、明治41年(1908年)夏以後の短歌が収録されています)
この歌は、歌集の第一部「我を愛する歌」にあります。
「我を愛する歌」の最初の十首は、砂浜や砂に関する連作短歌となっており、石川啄木の生き方やこの歌集を世に問う意味を暗示的に詠んだ歌が収められています。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「いのちをもたない砂というものは、なんとも悲しいものだ。手ですくって握りしめれば、さらさらと指の間からこぼれ落ちてしまう。」
となります。
この歌は、手ですくいあげた砂がさらさらと指の間からこぼれ落ちていく様子を詠んでいます。もろさや不安定さも感じさせる抒情的な歌です。
文法と語の解説
- 「いのちなき」
「なき」は形容詞「なし」の連体形です。
- 「砂のかなしさよ」
「の」は連体修飾格の格助詞です。「かなしさ」は、形容詞「かなし」の名詞化したもの。「よ」は詠嘆の終助詞です。
- 「さらさらと」
「さらさらと」は副詞。物の様子をそれらしく表した擬態語でもあります。
- 「握れば指の」
「握れば」は動詞「握る」の已然形「握れ」+条件を表す接続助詞「ば」です。
「の」は連体修飾格の格助詞です。
- 「あひだより落つ」
「より」は起点を表す格助詞。「落つ」は、動詞「落つ」終止形です。
「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、一首の中の意味の上での大きな切れ目をいいます。普通の文でいえば、句点「。」のつくところで切れます。
この歌は、二句目「かなしさよ。」ののところで句点がつきますので、「二句切れ」の歌です。
字余り
短歌は、五・七・五・七・七の音数で作っていくことが基本原則です。しかし、あえて規程の音数を外して詠むこともあります。
この歌は、以下のように2句目が八音になっており、「字余り」。となります。
「いのちなき(5) すなのかなしさよ(8) さらさらと(5) にぎればゆびの(7) あいだからおつ(7)」
字余りを用いることで、リズムをあえて崩し、作者の感じた「かなしさ」をより印象的に表現しています。
擬態語
擬態語とは、直接に音響とは関係のない状態を描写するのに用いられる言葉です。
例えば、「ふわふわとした雲」「太陽がぎらぎらと照る」の「ふわふわと」や「ぎらぎらと」が擬態語です。
この歌では、「さらさらと」という擬態語が使われています。砂が乾いていること、固まることなく流れるようにこぼれ落ちるさまを的確に表現しています。
「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」が詠まれた背景

この歌は、歌集の第一部「我を愛する歌」の中の砂浜や砂に関する連作短歌の八首目にあたります。
この歌では、手ですくいあげた砂がさらさらと指の間からこぼれ落ちていく様子を詠んでいます。この連作の中で、手で砂をすくっている歌がもう一つあります。
歌集『一握の砂』のタイトルの由来ともなった以下の歌です。
「頬につたふなみだのごはず一握の砂を示しし人を忘れず」
(意味:頬に伝う涙をぬぐうこともせず、一握りの砂を示してくれた人のことを忘れることはない。)
「一握の砂」という言葉が何を示すのか、解釈が分かれる歌です。感受性の鋭い作者の胸にあふれる想いからしたら、歌を詠むことで表しうる胸の内は、「一握の砂」のようにわずかなもので、作者は涙を流して苦しみながら短歌を生み出しているのだ、とも読めます。つまり、「一握の砂」は、作者が生み出す短歌をたとえた言葉だという解釈です。
「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」の歌では、握ってもさらさらと指の間からこぼれていく砂を詠んでおり、はかなさ、もどかしさを感じさせる歌です。
作者は、「頬につたふ…」の歌で、自らの歌を「一握の砂」にたとえていましたが、この歌では、短歌を詠んでも詠んでも、自分の想いを表現しきれないもどかしさや苦しさを詠んでいると解釈できるでしょう。
「いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ」の鑑賞

この歌は、寂寞とした切なさの漂う一首です。
「いのちなき砂」という出だしの言葉や、「さらさらと」という擬音語から、乾いた、無機的な印象を受けます。
「砂をにぎってすくいあげてもさらさらとこぼれ落ちていく」という動きからは、成果を求めて努力し、それをつかみ取ったと思っても、指の間から砂がこぼれ落ちてなくなっていくかのように、消え去ってしまうというような虚無感があります。
努力しても報われないむなしさ、もどかしさ、虚無感といった作者の感情が漂っています。
そういった気持ちを作者は「かなしさよ」という言葉でシンプルにまとめ、長い溜息をつくかのようです。
また、砂が落ちるという語感から、砂を落として時の経過を計る、砂時計のイメージも重なります。
砂がさらさらとこぼれ落ちるように、とどまることなく流れていく時。移ろい行くものの儚さや、諸行無常の感覚も感じられる歌です。
作者「石川啄木」を簡単にご紹介!

(1908年の石川啄木 出典:Wikipedia)
石川啄木(いしかわ たくぼく)は、明治時代後期に活躍した詩人であり、歌人です。本名は一(はじめ)と言いました。明治19年(1886年)、岩手県出身です。明治45年(1912年)、故郷を離れた東京でわずか26歳の生涯を閉じました。
啄木は岩手県の渋民村(現盛岡市渋民)で育ち、盛岡中学に在学中から、詩歌雑誌『明星』を愛読します。明治35年(1902年)、16歳の時に上京。しかし2年後には結核療養のために帰郷しました。
その後、父の金銭に関わるトラブルのため、一家で実家のあった渋民村を出なければならなくなりました。
新婚の妻、その後生まれた長女、両親らを養うため、啄木は盛岡や北海道で職を転々としました。明治41年(1908年)、再び上京を決意します。
東京でも、生活苦にあえぎながら創作活動を続けました。明治43年(1910年)には第一歌集『一握の砂』を刊行しました。
しかし、結核が悪化、第二歌集出版の話もある中で、明治45年(1912年)4月13日、石川啄木は儚い生涯を終えました。
「石川啄木」のそのほかの作品

(1904年婚約時代の啄木と妻の節子 出典:Wikipedia)
- やはらかに柳あをめる北上の岸辺目に見ゆ泣けとごとくに
- 馬鈴薯の薄紫の花に降る雨を思へり都の雨に
- 東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる
- 頬につたふなみだのごはず一握の砂を示しし人を忘れず
- 砂山の砂に腹這ひ初恋のいたみを遠くおもひ出づる日
- かにかくに渋民村は恋しかりおもいでの山おもいでの川
- はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢっと手を見る
- 石をもて追はるるごとくふるさとを出でしかなしみ消ゆる時なし
- 病のごと思郷のこころ湧く日なり目に青空の煙かなしも
- 不来方のお城の草に寝転びて空に吸はれし十五の心
- ふるさとの山に向ひて言ふことなしふるさとの山はありがたきかな
- たはむれに母を背負ひてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆまず
- 友がみなわれよりえらく見ゆる日よ花を買ひ来て妻としたしむ
- ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく