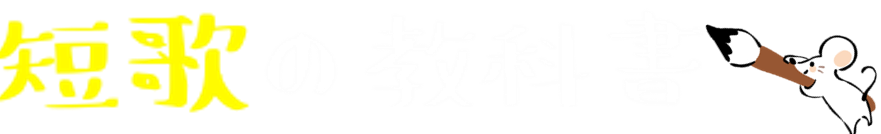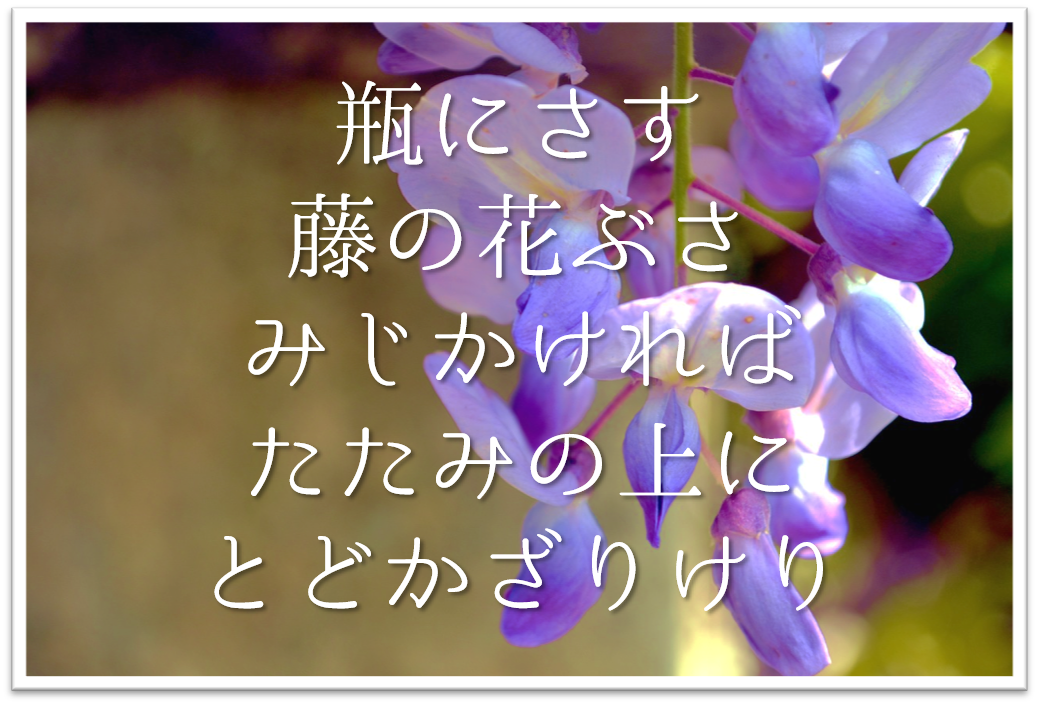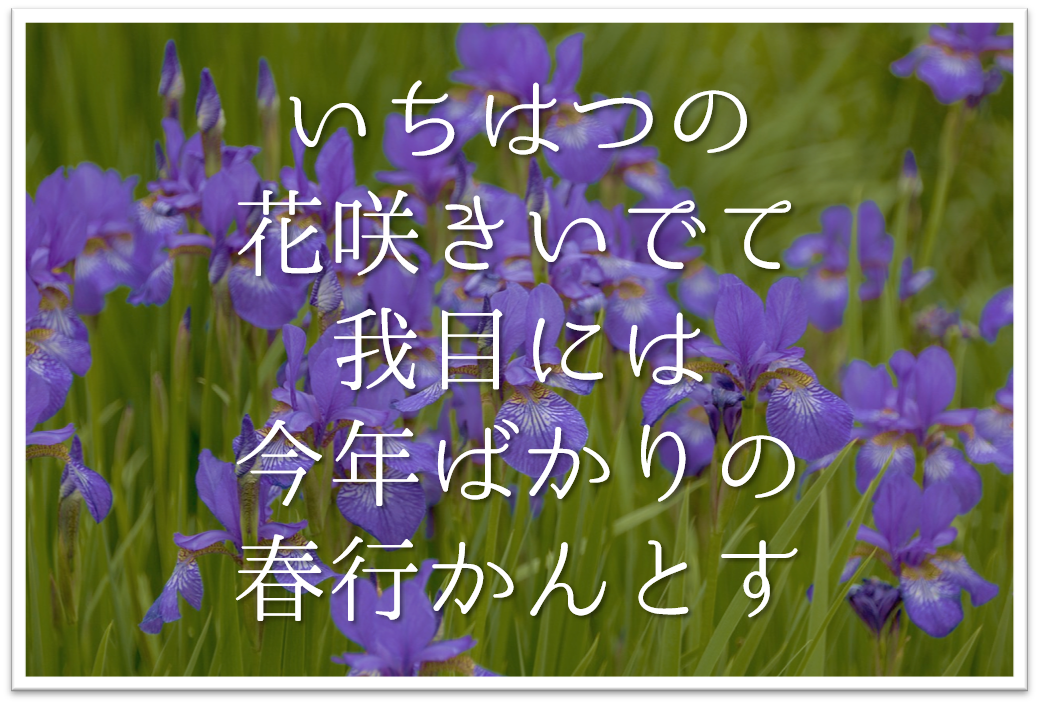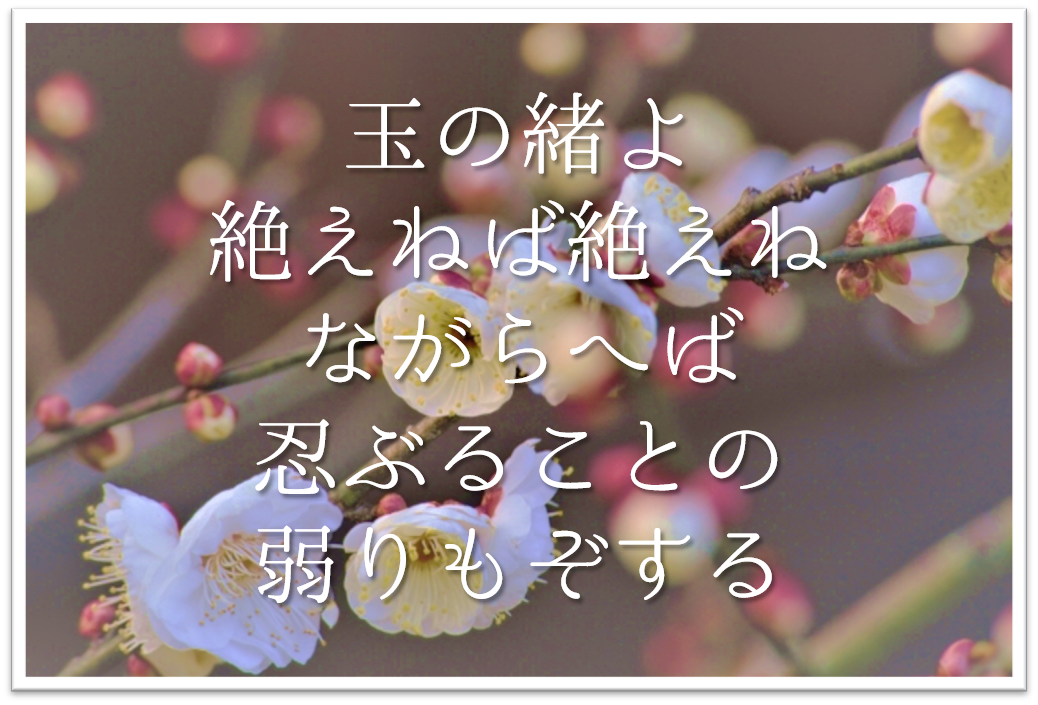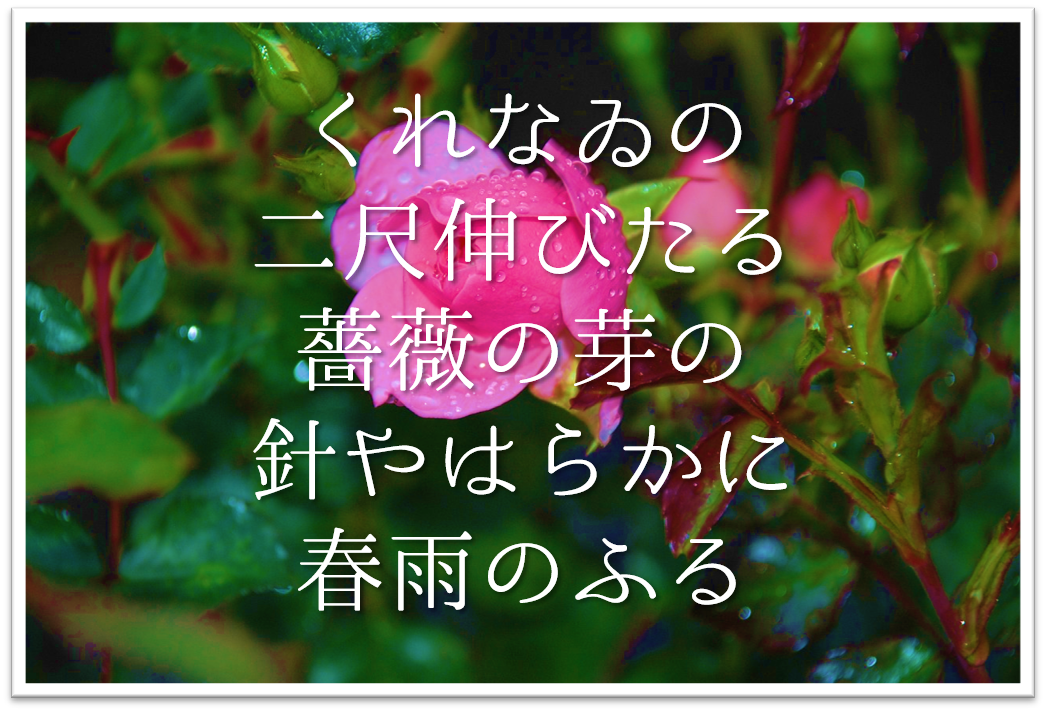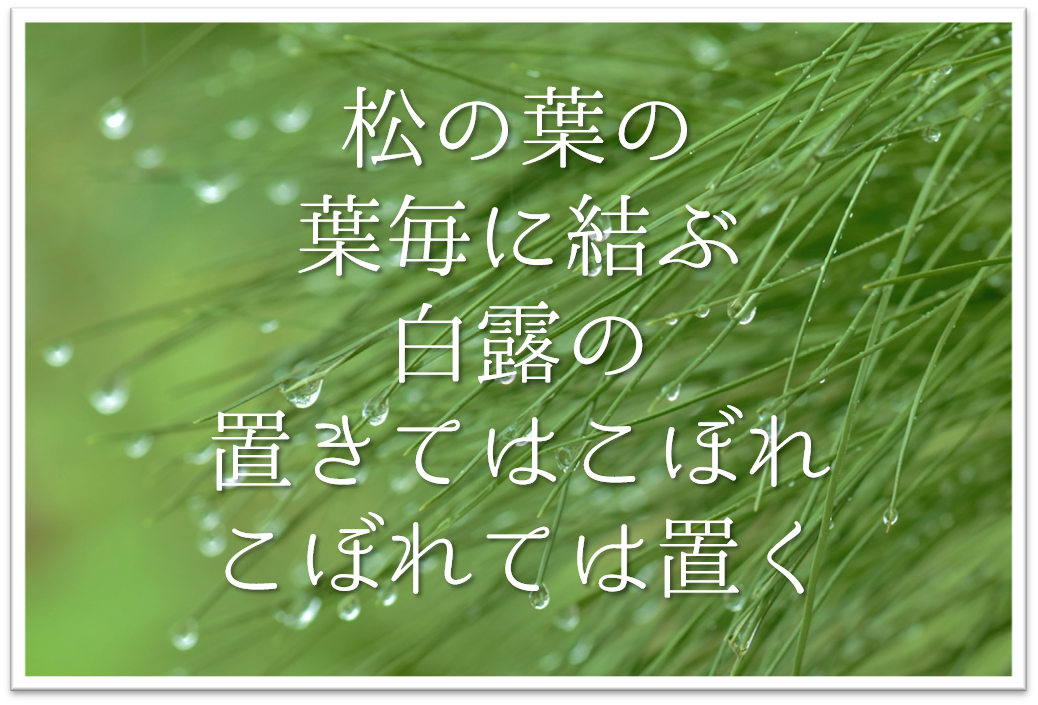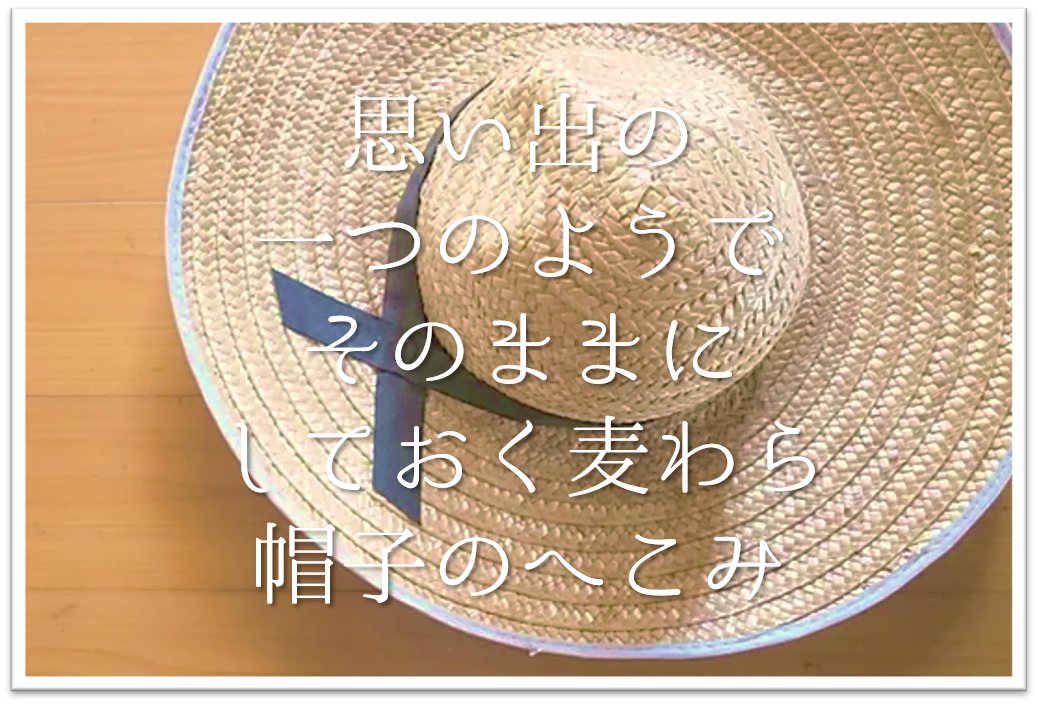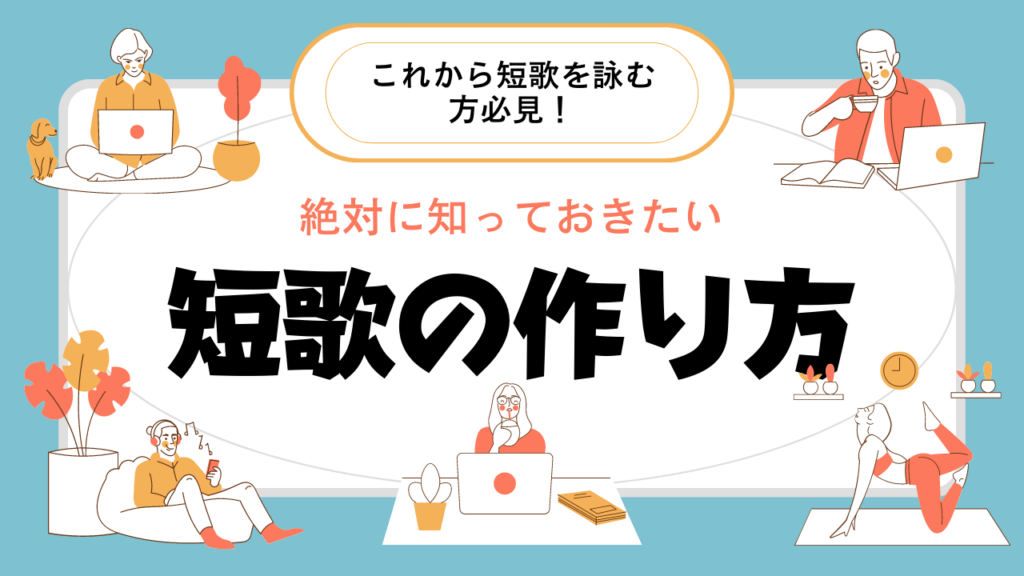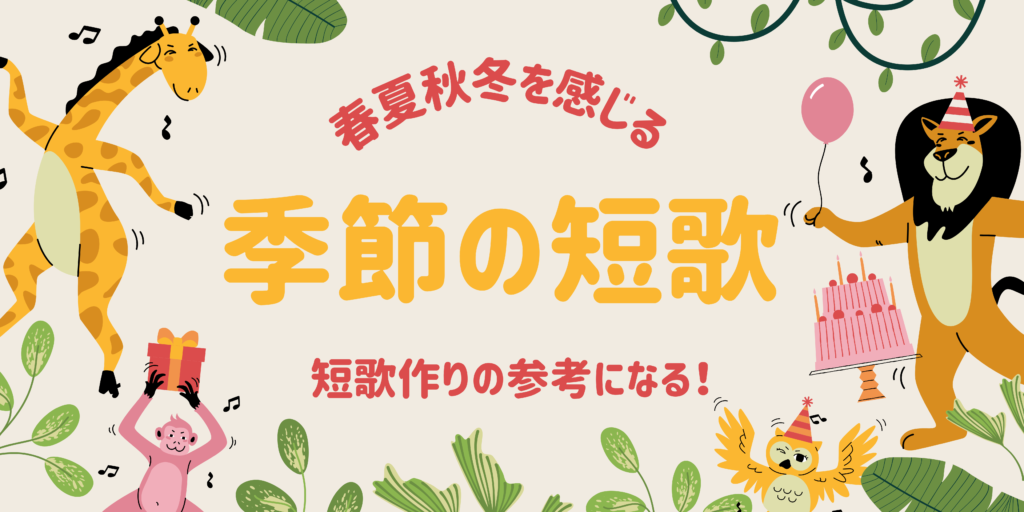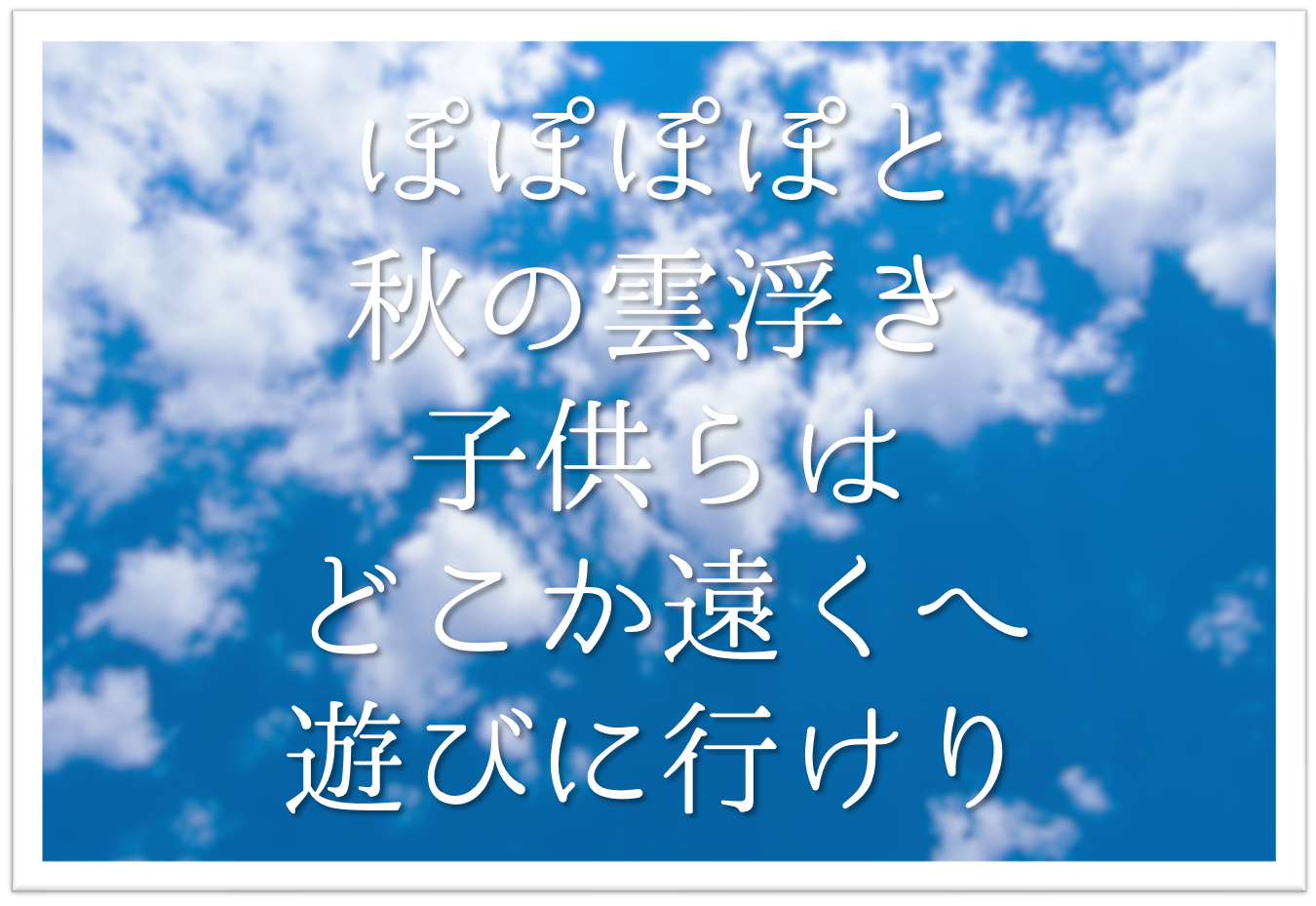
短歌は、5・7・5・7・7の31音で思いや考えを表現する定型詩です。
日本特有の短い詩は、『百人一首』が作られた平安時代に栄えていたことはもちろん、古代から1300年を経た現代でも多くの人々に親しまれています。
今回は、河野裕子の歌「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」をご紹介します。
ぽぽぽぽと 秋の雲浮き 子供らは どこか遠くへ 遊びに行けり
何回聞いてもじわる…笑— 太一 (@O2000Taichi) December 15, 2016
本記事では、「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」の詳細を解説!

ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり
(読み方:ぽぽぽぽと あきのくもうき こどもらは どこかとおくへ あそびにいけり)
作者と出典
この歌の作者は「河野裕子(かわの ゆうこ)」です。
戦後を代表する女性歌人で、平成の与謝野晶子とも呼ばれました。自身の恋愛や家族のことを詠んだ歌が多く、特に 同じく歌人である夫・永田和宏さんと交わした相聞歌は有名で、何百首も残されています。乳がんと闘病の末、2010年に亡くなりました。
また、この歌の出典は『紅』です。
1991年、ながらみ書房より刊行された、作者の第5歌集です。8年間ほどの、比較的長い期間の作品から593首が収められています。表題は娘:永田紅さんの名前からつけられています。娘の名前を意識したというよりは、「あまり意味のない、暖かそうなイメージのある言葉を探していたら、『紅』にゆきあたった」と作者は語っています。
現代語訳と意味 (解釈)
この歌は、古い仮名づかいを用いてはいますが、現代語で詠まれている歌です。
現代風の言い回しにすると・・・
「ぽぽぽぽと(いうような感じで)秋の雲が浮いていて、子供たちはどこか遠くへ遊びに行った。」
といった内容になります。
文法と語の解説
- 「ぽぽぽぽと秋の雲浮き」
「ぽぽぽぽ」は、雲が空に浮かぶ様子を表すオノマトペです。実際に雲がこのような音を出すわけではないので、これは擬態語です。「秋の雲」と聞いて一般的にイメージされるのは「うろこ雲」「いわし雲」などと呼ばれる巻積雲の一種です。おそらく作者もこれらのような雲のことを詠んでいるのでしょう。「雲」と「浮き」の間は、係助詞が省略されています。
- 「子供らは」
「子供ら」の「ら」は漢字で書くと「等」で、複数人いることを表します。つまり、この歌に出てくる子どもは1人ではないということが分かります。
- 「どこか遠くへ遊びに行けり」
「行けり」は動詞「行く」+過去を表す助動詞「けり」なので、子供たちはすでに遊びに行ってしまったのだということが分かります。
「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」の句切れと表現技法

句切れ
この歌は二句切れです。
初句と2句では、空に秋の雲が浮いている「見上げた情景」を描き、3句からは視点が地上に下りてきます。
オノマトペの使用
雲の様子を表すために「ぽぽぽぽ」という擬態語を用いています。
これはこの歌の一番の特徴とも言えるでしょう。読み手が情景を想像しやすいだけでなく、一度読めばしっかりと記憶に残る、とても印象的な表現です。
「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」が詠まれた背景

作者である河野裕子さんは、自身の恋愛や家族のことを多く歌に残しています。
とても多作な歌人で、日常の中で自然に歌を詠んでいたようで、生涯で作った作品数は数万になるのではと言われています。
「ぽぽぽぽと…」の歌は、作者の子どもたちが小学校~中学校に通っていた頃に詠まれました。この頃のことを、娘の永田紅さんは「純粋に子供時代と呼べる時代」と綴っています。
作者は母親として毎日ドタバタと騒々しく過ごす中で、元気いっぱいの子どもたちを見ながら、ふと感じた気持ちを歌にしたのでしょう。
「ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり」の鑑賞

【ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり】は、とある秋の日の何気ない風景を詠んだ歌です。
秋の晴れた日は、空気が澄んで空が高く見えます。「ぽぽぽぽ」という音が鳴りそうな可愛らしい雲がいくつも浮かび、うろこ雲になっている…、とても気持ちが良い気候なのでしょう。
そんな中、子供たちは元気いっぱいに遠くへ駆けていきます。歌の主人公は、子供たちの母親でしょうか。父親や他の家族、もしくは学校の先生なのかもしれません。子どもたちが駆けていく姿を、優しく見守っているようなあたたかさが感じられます。
良く晴れた日、思わず外に出て遊びに行きたくなる子供たちと、それを見守る主人公・・・。よくある日常の一風景ですが、とても幸せな生活が浮かび上がる一首です。
作者「河野裕子」を簡単にご紹介!

河野裕子さんは、1946年(昭和21年)に熊本県で生まれました。
中学時代には早くも歌づくりを始め、京都女子大学在学中に第十五回角川短歌賞を受賞しました。平成14年には「歩く」で若山牧水賞・紫式部賞を、平成21年には「母系」で斎藤茂吉短歌文学賞・迢空賞を受賞するなど、生涯を通して、また亡き後も含め、数々の賞に輝きました。
夫であり歌人の永田和弘とは歌壇きってのおしどり夫婦と言われています。大学時代に出会い、40年間にわたって交わした相聞歌は、河野さんのものだけでも500首近く残されています。
晩年には乳がんを患い、2010年に64歳で生涯を閉じました。亡くなる前日まで短歌を作り続けたと言われています。彼女の死後は、夫・息子・娘ら家族がそれぞれの著書で母:河野裕子について語っています。
「河野裕子」のそのほかの作品

- 振りむけばなくなりさうな追憶のゆふやみに咲くいちめんの菜の花
- たとへば君ガサッと落葉すくふやうに私をさらって行ってはくれぬか
- たつぷりと真水を抱きてしづもれる昏き器を近江と言へり
- 子がわれかわれが子なのかわからぬまで子を抱き湯に入り子を抱き眠る
- 後の日々再発虞れてありし日々合歓が咲くのを知らずに過ぎた
- 何年もかかりて死ぬのがきつといいあなたのご飯と歌だけ作つて