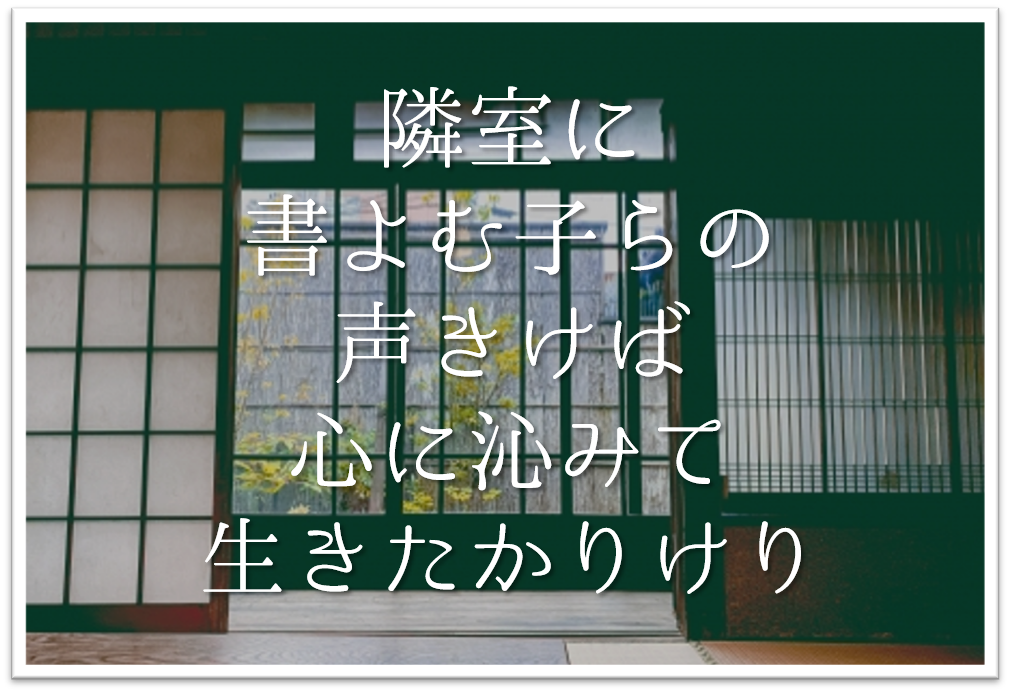
短歌は、五・七・五の俳句より、十四文字多い分だけ、俳句とはまた異なる抒情性や奥行きを持った詩となります。
その歌風も様々で、歌人によってそれぞれ独自の境地が切り開かれてきました。今まで数多くの名歌が詠まれてきています。
今回は明治時代から大正時代にかけて活躍した歌人・島木赤彦の名歌「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」をご紹介します。
隣室に書(ふみ)よむ子らの声きけば
心に沁みて生きたかりけり
島木 赤彦
#折々のうた三六五日#三月五日 pic.twitter.com/4HAc9Z7tVC
— 菜花 咲子 (@nanohanasakiko2) March 6, 2017
本記事では、「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」の歌の意味や表現技法・句切れについて徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」の詳細を解説!

隣室に 書よむ子らの 声きけば 心に沁みて 生きたかりけり
(読み方:りんしつに ふみよむこらの こえきけば こころにしみて いきたかりけり
作者と出典
この歌の作者は、「島木赤彦(しまきあかひこ)」です。
島木氏は、諏訪藩(現在の長野県)の藩士の家柄に生まれた人物で、明治時代から大正時代に活躍した歌人です。
この歌の出典は『柿蔭集(しいんしゅう)』、大正15年(1926年)刊です。
この歌集は大正13年(1924年)から、作者が没する大正15年(1926年)の歌がおさめられています。島木赤彦の死後に刊行されました。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「隣の部屋で書を読み上げるこどもらの声を聞くと、心からしみじみと、生きたいと思うことだ。」
となります。
文法と語の解説
- 「隣室に」
「に」は存在の場所を表す格助詞です。
- 「書読む子らの」
「書」は「ふみ」と読みます。書物を子どもたちが声に出し音読しているのです。
「の」は連体修飾格の格助詞です。
- 「声聞けば」
「聞けば」は動詞「聞く」の已然形「聞け」+接続助詞「ば」です。
- 「心に沁みて」
「に」は対象を表す格助詞です。
「沁みて」は動詞「沁む」の連用形「沁み」+接続助詞「て」です。
- 「生きたかりけり」
「生きたかりけり」は、動詞「生く」の連用形「生き」+希望の助動詞「たし」の連用形「たかり」+詠嘆の助動詞「けり」です。
「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、意味や内容、調子の切れ目を指します。歌の中で、感動の中心を表す助動詞や助詞(かな、けり等)があるところ、句点「。」が入るところに注目すると句切れが見つかります。
ただ、この歌に句切れはありませんので、「句切れなし」となります。
生きることへの渇望を一息に歌に込めています。
表現技法
この歌に用いられている表現技法は特にありません。
「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」が詠まれた背景

この歌は、作者島木赤彦の亡くなる前の月に詠まれた歌です。彼の死後まとめられた歌集『柿蔭集』におさめられました。
島木赤彦は、大正15年(1926年)1月、居住していた長野県上諏訪の医師から胃がんの診断を受けます。そして、それを心配した雑誌『アララギ』の歌人にして盟友、医師でもある斎藤茂吉が翌月の2月に東京の病院の受診をすすめましたが、がんの診断は覆ることはありませんでした。
「隣室に…」の歌は、『柿蔭集』の中の「大正十五年」の章にあり、実はこの年の1月に島木氏にがんの診断が下っています。
この章は「恙(つつが)ありて」という連作から始まっています。「恙(つつが)」とは、病気のこと。つまり、病を得た自分と向き合う歌の連作なのです。
ここでは、連作「恙ありて」から、何首か抜粋してご紹介します。
「今にしてわれは思ふいたづきをおもひ顧みることもなかりき」
(現代語訳:今にして思うと、病気のことを顧みて我が身をいたわることをしてこなかった。※「いたづき)とは病気のこと。)
「みづうみの氷をわりて獲し魚を日ごとに食らふ命生きんため」
(現代語訳:湖の氷を割って取った魚を毎日食べていることだ、命をながらえさせるため。)
「恙ありて一・二」に続くのは、「二月一日」という連作です。病状はさらに悪化、作者は死を意識するようになることが歌われています。連作「二月一日」からも抜粋してご紹介しましょう。
「もろもろの人ら集(こぞ)りてうち臥(こや)す我の体を撫で給ひけり」
(現代語訳:たくさんの人が集まって、病に伏す私の体を撫でてくださることよ。)
「わが腰の痛みをさすり給ひけるもろもろ人を我は思ふも」
(現代語訳:私の腰の痛みをさすってくださる皆さんのことを、私は思っている。)
これらの歌は、己の病気を心配して東京での受診に付き添ってくれた斎藤茂吉や太田水穂(島木赤彦と長野県尋常師範学校の同級生で歌人)らに対する謝意とも読めます。
2月13日には、昼夜を問わない痛みに苦しみ、やせ細っているとの記述(下記)もあります。
「火箸持て野菜スープの火加減を折々見居り妻の心あはれ」
(現代語訳:火箸をもって、私のために煮ている野菜スープの火加減を見ている妻の心のうちを思うとあわれでならない。)
「隣室に書をよむ子らの声聞けば心に沁みて生きたかりけり」
(現代語訳:隣の部屋で書を読み上げるこどもらの声を聞くと、心からしみじみと、生きたいと思うことだ。)
病床にあって、家族のことを痛切に思います。やせ細り、病み衰えた自分のために野菜スープを煮ている妻。病室の隣の部屋で勉強をしている子どもたち。「隣室に書よむ子ら」とは、18歳になる三女と16歳の四男のことであったともいわれます。
友人、家族を思う歌に連なるのは、ふるさとのことです。
「信濃路はいつ春ならん夕づく日入りてしまらく黄なる空のいろ」
(現代語訳:信濃路が春になるのはいつのことか。夕日が沈み、しばらく黄色みを帯びた空が広がることだ。)
春の到来を見届けることができるのかどうかと己の命をはかる思い、尽きせぬ故郷への愛着を感じさせる歌です。この歌は、島木赤彦の代表作としてもよく知られています。
「魂はいづれの空に行くならん我に用なきことを思ひ居り」
(現代語訳:魂は空のどこに行くものだろうか。この世に、もう私の用事は残っていないのだと思い過ごしている。)
作者は、はっきりと死を意識しています。
『柿蔭集』の最後の2首は、看病にあたる家族をおもんぱかり、残される飼い犬のことを心配する歌です。
3月16日の詠
「たまさかに吾を離れて妻子らは茶をのみ合へよ心休めに」
(現代語訳:たまには、病人の私をはなれ、妻よ、子よ、気晴らしに茶でも飲んでくれ。)
大正15年(1926年)3月27日、島木赤彦、本名久保田俊彦は永眠しました。享年49歳でした。
「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」の鑑賞

「隣室に書・・・」は、子を持つ親として、生きることへの愛惜、渇望をうたい上げた一首です。
「書よむ子ら」も父の病気を心配し、もしかしたら声高らかに音読していたわけではないかもしれません。
しかし、それでも育ち盛りの子らの声には、命のエネルギーがあふれているように、病に臥せる父の耳には聞こえたことでしょう。
これから人生を謳歌する我が子ら、父として近くで彼らの成長を見守り、世間の荒波から守ってやる術が失われつつあることを痛切に嘆く、父親の絶唱です。
平明な言葉で詠まれており、ひたひたと生きたいという思いが胸に迫る歌です。
作者「島木赤彦」を簡単にご紹介!

(島木赤彦 出典:Wikipedia)
島木赤彦(しまぎあかひこ)は本名久保田俊彦(くぼたとしひこ)です。明治9年(1876年)、長野県の旧諏訪藩士塚原浅茅の四男・塚原俊彦として生まれました。
幼い頃から、歌道の心得のあった祖母や、国学者であった父の薫陶を受けて育ちます。本格的に短歌や新体詩を作り始めたのは10代半ばのころでした。
長野県尋常師範学校(現 信州大学教育学部)に進み、同級生に太田水穂らがいました。歌作、句作に加え、文芸雑誌『文学界』で活躍していた島崎藤村にも影響を受けて詩作に励みました。
明治31年(1898年)、久保田正信の養嗣子として、久保田家の長女うたと結婚、数年後、うたが亡くなるとうたの妹ふじのと再婚しました。
島木赤彦は、文芸雑誌『アララギ』に深くかかわっていくようになります。『アララギ』は、正岡子規が始めた根岸短歌会がその源となっており、子規に師事した伊藤佐千夫が斎藤茂吉らとともに、子規の短歌における精神の継承を唱えて中心となって活動していました。伊藤佐千夫、斎藤茂吉と親交のあった島木赤彦は『アララギ』にも関わるようになるのです。大正3年(1914年)、島木赤彦は長野県での職を辞し上京、『アララギ』の編集や発酵に関わることとなりました。
島木赤彦は、歌作において「鍛錬道」「一心集中」ということを唱えました。つまり、一つのことに専心し、厳しい修行をするというようなことです。
島木赤彦は、正岡子規の提唱した写生論を引き継ぎながら、独自の写生論を展開しました。島木赤彦の家風は「寂寥相」ともいわれ、島木赤彦の歌に対する姿勢は厳しく、その反面として『アララギ』の歌風は狭いものになっていきました。
しかし、大正15年(1926年)1月には胃がんの診断が下り、3月下旬に帰らぬ人ととなりました。第五歌集『柿蔭集』は、その年の7月に遺歌集として発行されました。
「島木赤彦」のそのほかの作品

- 夕焼空焦げきはまれる下にして氷らんとする湖のしづけさ
- 月の下の光さびしみ踊り子のからだくるりとまはりけるかも
- ひたぶるに我を見たまふみ顔より涎を垂らし給ふ尊さ
- みづうみの氷は解けてなほ寒し三日月の影波にうつろふ
- 信濃路はいつ春ならん夕づく日入りてしまらく黄なる空のいろ












