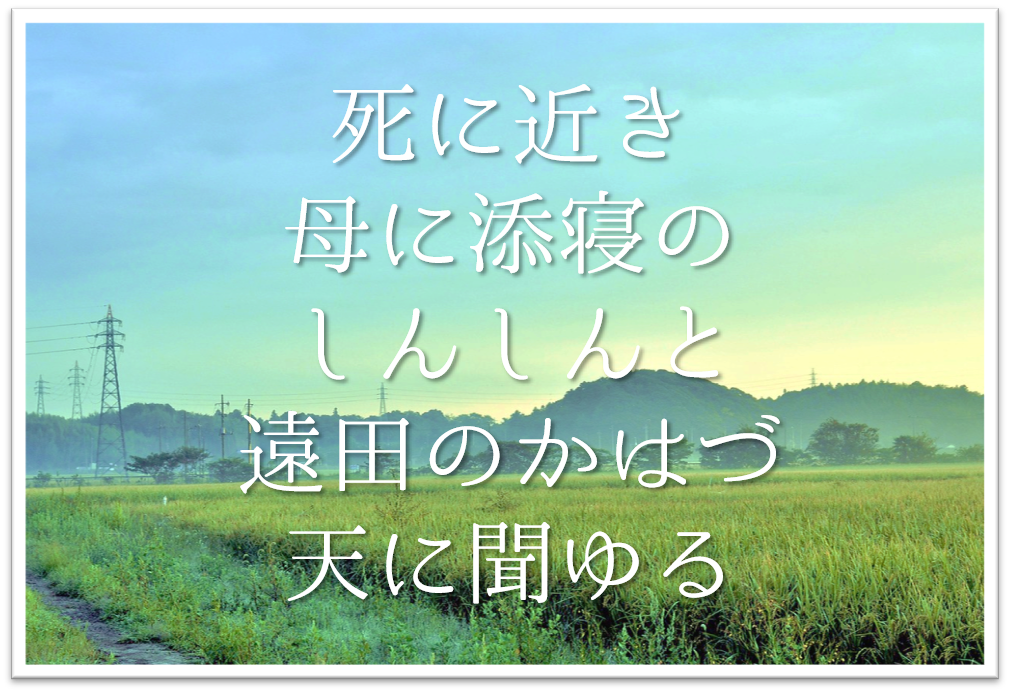
近代における短歌の発展は目覚ましいものがあり、数多くの作品が詠まれてきています。
人生の歓びや苦しみ、悲しみを詠った歌、生活の中で沸き起こった感興、美しい自然への崇敬、様々な思いが短歌の調べの中で表現されてきました。
今回は、精神科医でもあり歌人でもあった斎藤茂吉の名歌「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」をご紹介します。
死に近き母に添寝(そひね)のしんしんと遠田(とほた)のかはづ天(てん)に聞(きこ)ゆる
斎藤茂吉#きょうの短歌https://t.co/39CctbDoG6 pic.twitter.com/c7NjURHfIC— 地獄極楽太夫 (@gokuraku_zigoku) February 7, 2019
本記事では、「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」の意味や表現技法・句切れについて徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」の詳細を解説!

死に近き 母に添寝の しんしんと 遠田のかはづ 天に聞ゆる
(読み方:しにちかき ははにそいねの しんしんと とおたのかわず てんにきこゆる)
作者と出典
この歌の作者は、「斎藤茂吉(さいとうもきち)」です。
山形県生まれの人物で、東京の医師の家に養子となって大学で医学を学び、医師として働きつつ、短歌も詠みました。
この歌の出典は、大正2年(1913年)発刊「赤光(しゃっこう)」「死にたまふ母」という連作短歌の中の一首です。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「死期の近い母に添い寝をしていると、遠くの水田で鳴きかわす蛙の声が天高く昇っていくように思われることだ。」
となります。
斎藤茂吉は、15歳で生家をはなれ、東京の医者の家に養子に出されました。大正2年(1913年)5月、生母が危篤との知らせを受けて、茂吉は一路、故郷山形の金瓶村に向かいます。医師の卵である茂吉でしたが、母にしてやれることはごく僅か。しかし、一刻一秒を大切に、母との濃密な時間を過ごしました。この歌は、母の看病中に病室で休んでいた時の歌です。
文法と語の解説
- 「死に近き」
「に」は格助詞です。
「近き」は形容詞「近し」の連体形です。
- 「母に添寝の」
「に」「の」は格助詞です。
「添寝」は、看病のために、母の病床の近くでやすんでいるということです。
- 「しんしんと」
「しんしんと」は副詞です。
この「しんしんと」という言葉が、何を言い表しているのか解釈が分かれるところです。
夜が更けていく様子とも取れますし、静まり返っていく中で、蛙の声だけが響き渡っている様子とも取れます。
- 「遠田のかはず」
「遠田」は「とおた」と読みます。遠くにある水田のことです。
「かはず」は、「かわず」と読み、蛙の古い言い方です。初夏から夏にかけて繁殖を行い、メスを求めてオスが大きな声で鳴きます。
- 「天に聞こゆる」
「に」は格助詞です。
「聞こゆる」は、動詞「聞こゆ」の連体形「聞こゆる」です。
「天に聞こゆる」とは、蛙の声が天まで昇っていくように、空高く響いている様を表しています。
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」の句切れと表現技法

句切れ
句切れとは、意味や内容、調子の切れ目を指します。
この歌には句切れはありませんので、「句切れなし」となります。
母に付き添って横たわりながら感じ取った情景を、一筆書きで描写するかのように切れ目なく詠みあげられています。
擬態語(オノマトペ)
擬態語とは、直接に音響とは関係のない状態を描写するのに用いられる言葉です。「ぐんぐんと成長する」の「ぐんぐんと」、「にっこりと笑う」の「にっこりと」などがそれにあたります。
この歌では、「しんしんと」という擬態語が用いられています。
この歌の「しんしんと」は、何の様子を表しているのか、解釈の分かれるところです。「しんしんと」という言葉は、夜がふけていく様や静まり返っている様を表すのによく用いられます。
天まで響くような蛙の声というのは、考えようによっては大きな音でうるさくにぎやかだろうとも思えますが、作者は蛙の声の響く夜更けを「しんしんと」と表現しました。母をもうすぐ喪うのだという現実を前に、作者の沈痛な・悲痛な気持ちも込められた言葉だとも考えられます。
この歌の上の句には、室内でかすかな呼吸をしつつも黄泉路に近づいている母、下の句では、外に広がる生き物の濃密ないのちの気配のある自然の世界が描かれています。
上の句の最後におかれた「しんしんと」という言葉によって、この歌の世界は母に付き添って看護にあたる室内の光景から、遠くに広がる水田で鳴く蛙の声が天まで届くかのように響く広い空間へと広がっていきます。
「しんしんと」という言葉はこの歌全体の奥行きを深める言葉でもあるといえます。
連体止め
連体止めとは、文末を連体形で止めて余韻を残す表現です。
この歌の結句は「聞こゆる」ですが、これは「聞こゆ」の連体形です。
歌の終わりの部分なので原則は終止形なのですが、あえて連体形にすることで蛙の声が響き渡っている様子を、余韻をもって表現しています。
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」が詠まれた背景

の歌は、斎藤茂吉の第一歌集『赤光』の中の、「死にたまふ母」という59首に及ぶ連作の中の一首です。
斎藤茂吉は山形県の農村、守谷家の三男として生まれますが、経済的事情から15歳の時に東京の斎藤家に養子に出されました。開業医である養父斎藤紀一の跡を継ぐべく、東京帝国大学医科大学を卒業。東大医科大学助手として学びつつ病院勤務をしていました。
大正2年(1913年)5月16日、斎藤茂吉は山形の実家の生母が危篤に陥ったとの報せを受け取り、帰郷の途につきます。
連作「死にたまふ母」は、以下のように四部で構成されています。
- 第一部・・・母のもとへ急ぐ帰郷の途上での思いを詠んだもの11首
- 第二部・・・母と過ごした最期の時間とその死14首
- 第三部・・・葬送14首
- 第四部・・・温泉行中にて母の喪うことの哀しみ思い返してを詠んだ20首
「死に近き…」の歌は、連作「死にたまふ母」の第二部にあります。
斎藤茂吉は危篤の母のもとへ薬をもって一散に帰郷し、わずかな看取りの時間を得ます。時は5月で初夏のころ合い、懐かしい故郷は生き物の生命のエネルギーに満ち満ち、水田では蛙がさかんに鳴きかわす時期でした。
そんな美しい季節に、母は死に向かおうとしているのです。母の傍らにあって最後の親子の時間を過ごす様子を詠んだ歌のひとつです。
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」の鑑賞

「死に近き母…」は、死に向かおうとしている母と、その周りの様子を写生的に詠んだ歌です。
蛙は昼間よりも夜の方がよく鳴き、またその鳴き声も響いて聞こえます。季節は夏のはじめ、蛙にとっては繁殖の時期であり、遠くの田で蛙が鳴いているのは新しい命が受け継がれていくことの証です。
その一方で、かけがえのない自分の母は死に近づいている、そのやりきれない尽きせぬ哀しみが「しんしんと」という言葉に込められています。
歌集『赤光』は、斎藤茂吉の第一歌集ですが、この歌集が世に出るとすぐに歌壇で注目を浴びました。母の死を悼む率直な歌、その真に迫る抒情性が多くの人の胸を打ったからです。
作者「斎藤茂吉」を簡単にご紹介!

(1952年頃の斎藤茂吉 出典:Wikipedia)
斎藤茂吉は、明治の終わりから昭和20年代にかけて活躍した精神科医であり、歌人でした。
生まれは明治15年(1882年)で、山形県南村山郡金瓶村の守谷伝右衛門熊次郎の三男として誕生しました。
自然豊かな山形の農村で、のびのび育ち、隣が寺だったということもあり、仏教にも親しんで成長しました。
茂吉が15歳の時に、経済的な事情から東京で開業医をしていた斎藤紀一が養子としてめんどうをみることになります。
都会に出た茂吉は文学にも興味を持ちました。旧制第一高校時代には正岡子規を知り、遺歌集『竹の里歌』に感動、作歌を始めたようです。短歌については、正岡子規の門弟、伊藤佐千夫の門に入り、雑誌『アララギ』(正岡子規が始めた根岸短歌会を源流にもつ文芸雑誌)で作品を発表、以降アララギ派を代表する歌人として活躍しました。
短歌の創作活動に励む一方、東京帝国大学医科大学を卒業、家業の病院を継ぐべく正式に医師になる前後に発表された第一歌集『赤光』は当時の歌壇で評判を呼び、そのごも『あらたま』、『つゆじも』などの多くの歌集、随筆集などを著述しました。
医師となったのちは、斎藤家の娘輝子と結婚しました。妻とは性格の合わないところも多々あり、順風満帆の家庭生活ではありませんでしたが、精神科医としても研究を続け、病院経営も行うなど、本業でも成果をあげました。
大正13年(1924年)、斎藤茂吉がヨーロッパ留学からの帰途にあるときに、斎藤紀一が院長をつとめる青山脳病院が失火により全焼、帰国した斎藤茂吉は病院の再建に力を注ぐこととなります。しかし、昭和には、戦火によって、再建のなった青山脳病院も自宅も全焼、故郷山形の金瓶村に疎開していた時期もありました。
昭和23年(1948年)には病院長を引退、その後も創作活動を続けましたが、昭和28年(1953年)、70歳で病没しました。
「斎藤茂吉」のそのほかの作品

- ただひとつ 惜しみて置きし 白桃の ゆたけきを吾は 食ひをはりけり
- 沈黙の われに見よとぞ 百房の 黒き葡萄に 雨ふりそそぐ
- みちのくの 母のいのちを 一目見ん 一目見んとぞ ただにいそげる
- 最上川の 上空にして 残れるは いまだうつくしき 虹の断片
- 猫の舌の うすらに紅き 手ざはりの この悲しさを 知りそめにけり
- 死に近き 母に添寝の しんしんと 遠田のかはづ 天に聞ゆる
- ものの行 とどまらめやも 山峡の 杉のたいぼくの 寒さのひびき
- 信濃路は あかつきのみち 車前草も 黄色になりて 霜がれにけり
- うつせみの 吾が居たりけり 雪つもる あがたのまほら 冬のはての日












