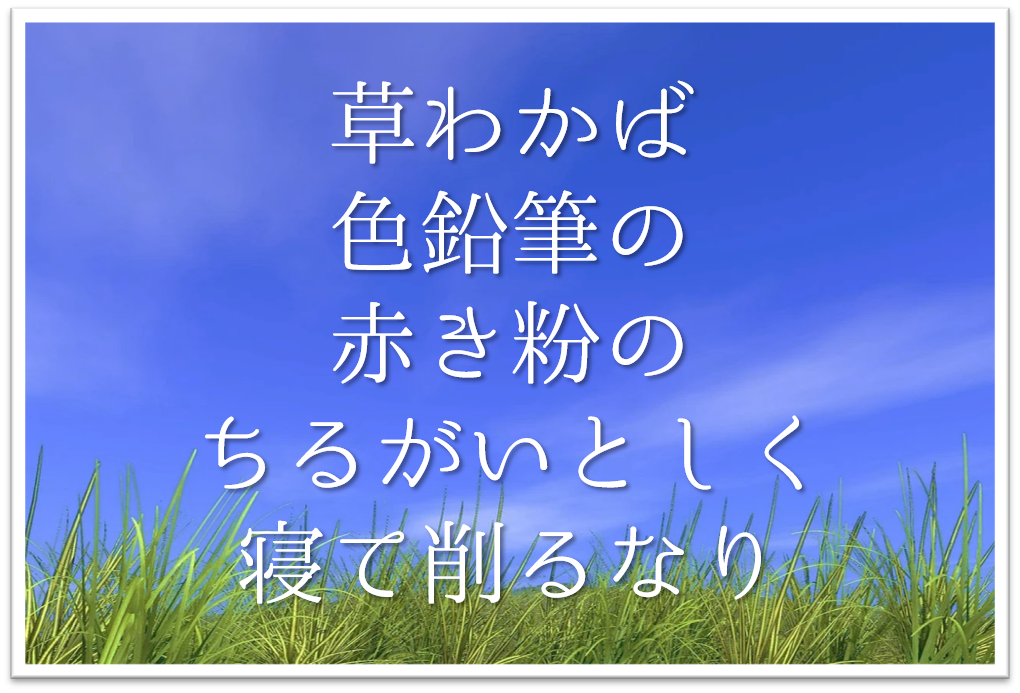
詩人、歌人、作詞家などマルチな文学の才能にあふれ、数々の美しい詩歌を発表した「北原白秋」。
彼は明治時代の終わりから、昭和の初めころまでを活躍した人物です。優しく美しい言葉で、抒情的な歌を多く残しました。
今回はそんな北原白秋の名歌「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」をご紹介します。
草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり
北原白秋.
風はちょっと冷たいけれど、土手散歩は今の季節が一番好きです♪
やっとツクシさん見つけました~~ヾ(^∇^)
#ツクシ #アカツメクサ
#カラスノエンドウ pic.twitter.com/BQcINjUtdd— 風に徘徊(多忙・気まぐれ浮上) (@w_viburnum) March 13, 2016
本記事では、「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」の意味や表現技法・句切れについて徹底解説し、鑑賞していきます。
目次
「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」の詳細を解説!

草わかば 色鉛筆の 赤き粉の ちるがいとしく 寝て削るなり
(読み方:くさわかば いろえんぴつの あかきこの ちるがいとしく ねてけずるなり)
作者と出典
この歌の作者は「北原白秋(きたはらはくしゅう)」です。白秋は明治時代末期・大正時代、昭和10年代に活躍した歌人であり、詩人です。
この歌の出典は、大正2年(1913年)発刊、『桐の花(きりのはな)』です。
桐の花は北原白秋の第一歌集です。雑誌『明星』の流れを汲む、抒情的でロマンチシズムあふれる歌風が歌壇で話題となりました。
現代語訳と意味(解釈)
この歌の現代語訳は・・・
「草わかばのもえぎ色に、色鉛筆の赤い粉が散っていく様がいとおしく思われて、草原に寝転んで色鉛筆を削ることだ。」
となります。
色鉛筆を削る手元に注目し、赤い色鉛筆の粉が草に散りかかる様子に焦点を当てた小さな世界の美を詠んだ歌です。
文法と語の解説
- 「草わかば」
「草わかば」とは、春になって柔らかく萌え出でた若い葉のことです。
- 「色鉛筆の」
「の」は連体修飾格の格助詞です。
- 「赤き粉が」
「赤き」は形容詞「赤し」の連体形「赤き」です。「が」は主格の格助詞です。
- 「ちるがいとしく」
「ちるが」は動詞「ちる」の連体形+格助詞「が」です。「いとしく」は形容詞「いとし」の連用形です。
- 「寝て削るなり」
「寝て」は、動詞「寝(ぬ)」の連用形の「寝(ね)」+接続助詞「て」です。
「削るなり」は動詞「削る」の連体形「削る」+断定の助動詞「なり」の終止形です。
「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」の句切れと表現技法

句切れ
この歌は初句「草わかば」で一旦意味が切れていますので、「初句切れ」となります。
初句の「草わかば」で色彩イメージを強く打ち出し、印象を強めています。
表現技法
この歌に用いられている表現技法は特にありません。
「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」が詠まれた背景

この歌は、明治43年(1910年)に詠まれた歌です。
明治41年(1908年)末ごろから、北原白秋はパンの会に参加していました。
パンとは、ギリシア神話に出てくる牧神にして芸術神。パンの会とは、東京の隅田川をパリのセーヌ川に見立て、西洋料理店にて浪漫派の新芸術を語り合うことが目的の会でした。
主宰は画家の松井柏亭で、他にも画家の山本鼎ら、詩人の木下杢太郎、長田秀雄ら、のちに高村光太郎も参加しました。パンの会が続いたのは、明治41年(1908年)末から5年程の間ですが、耽美的な傾向が強い芸術運動の場となっていました。
北原白秋のこのころの作品は、西欧的な異国情緒、感傷的なロマンチシズムのあふれる作風となっていました。
この「草わかば色鉛筆の…」の歌は、北原白秋の第一歌集『桐の花』の中の、「晩春初夏」の章の、「公園のひととき」という連作短歌の中の一首です。この「公園のひととき」という連作は、シャンソンが流れるフランス映画のような趣が感じられる作品群です。
まず、「草わかば色鉛筆の…」の前に連なる歌をご紹介します。
草わかば黄なる小犬の飛び跳ねて走り去りけり微風(そよかぜ)の中
(現代語訳:もえぎ色の若い草原の中を、黄色い小犬が飛びはねて駆け去っていったことだ、そよ風の吹く中を。)
草わかば踏めば身も世も黄に染みぬ西洋辛子(からし)の粉を花はふり撒く
(現代語訳:もえぎ色の若い草の葉を踏み分け歩くと、私の体も、あたりも黄色く染め上げられたように感じることだ。西洋辛子菜の花は黄色い花粉をあたりに振りまいている。)
※西洋辛子は、アブラナ科の植物。アブラナ科の花を総称して菜の花という
こころもち黄なる花粉のこぼれたる薄地のセルのなで肩のひと
(現代語訳:ほんのりと黄色い花粉がこぼれた薄地の服を着たなで肩の人がたたずんでいることよ。)
※セルは薄手の着物地、服地のこと。春先に着られる。
「草わかば」「黄色い小犬」「黄に染みぬ」「西洋辛子」の花、「黄なる花粉」と、色彩感あふれる歌が並びます。
この三首に続いて、「草に寝ころべ、草に寝ころべ」という詞書がついて、今回解説する一首が登場します。
「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」
(現代語訳:草わかばのもえぎ色に、色鉛筆の赤い粉が散っていく様がいとおしく思われて、草原に寝転んで色鉛筆を削ることだ。)
前の三首が、「草わかば」のもえぎ色と、子犬や西洋辛子菜の花の黄色がテーマカラーでしたが、この「色鉛筆」の歌で鮮やかな赤が加わります。空の色まで歌の中で言及はありませんが、ここは澄んだ青空が広がっているのでしょう。
「草に寝ころべ、草に寝ころべ」という、呼び掛けるような口調の繰り返しの詞書からも、若々しい心の弾みや、軽やかさが伝わってきます。
「草わかば色鉛筆の赤き粉・・・」に続く歌とは?
この歌に続くのは、以下の一首です。
「夕されば棕梠の花ぶさ黄に光る公園の外に座る琴弾者(ことひき)」
(現代語訳:夕暮れてくると、棕梠(シュロ)の花の房が黄色く光って見えることだ。公園の外には、座って琴を弾く者がある。)
※棕梠とは、ヤシ科シュロ目の木の総称。異国情緒のある木。
「琴弾者(ことひき)」が、具体的にどんな琴を弾く奏者なのかわかりませんが、この歌集『桐の花』の冒頭のエッセイで、北原白秋は自らの短歌を、哀愁を帯びた「一弦琴」の音色と結び付けて語っています。
「短歌は一箇の小さい緑の古宝玉である。(中略)その完成した美しい形は東洋人の二千年来の悲哀のさまざまな追憶 (おもひで)に依てたとへがたい悲しい光沢をつけられてゐる。その面には玉虫のやうな光や(中略)一絃琴や古い日本の笛のやうな素朴な(中略)リズムが動いてゐる。」
(現代語訳:短歌は、私にとって一つの小さな緑色の古い宝石のようなものである。長い年月の間に完成された短歌のスタイルは美しく、二千年もの間、人々の悲哀や追憶が詠まれてきたことを思うと、短歌とは悲しくも美しいものだと思う。短歌には、いわば玉虫のような光をはなち、一弦琴や笛の音のような素朴なリズムが息づいていると私は考えている。)
「夕されば…」の歌は、一弦琴のもの悲しい調べに彩られた春の夕暮れの愁いを詠んだ一首なのです。
このように、連作「公園のひととき」を読んでいくと、春の陽ざしのもとで過ごす心弾む公園でのひととき、そして夕暮れの春愁が洒落た映画でも見るようにイメージされます。やわらかく春らしい美しい色彩のもの、哀愁を帯びた琴の音が歌の世界の雰囲気を高めています。
これらの歌は、実景を詠んだものというより、北原白秋の描く美の世界を短歌で表現したものといえるかもしれません。
「草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり」の鑑賞

前項で解説した通り、この歌は連作短歌の中の一首でですが、この一首だけを取り出し、日常の些細な動作に見出したささやかな美しさを詠んだ一首として鑑賞しても十分それに耐えうる秀逸な歌です。
「草わかば」の鮮やかなもえぎ色と、色鉛筆の赤という補色関係になる色の対比がとても鮮烈で、色彩イメージの豊かな歌となっています。
やわらかな緑色の若い草の葉に、色鉛筆の粉が散る一瞬の儚い美しさを楽しむには、草原に自らも寝転んで色鉛筆を削るよりほかありません。
やわらかな草の感触や土のにおい、穏やかな日の光やそよ風といったものも感じさせてくれる、抒情性とイマジネーションに富んでいます。
この歌は青春の感傷とロマンチシズムにあふれ、多くの若者、そしてかつて若者だった人たちの共感を呼んでいます。
作者「北原白秋」を簡単にご紹介!

(北原白秋 出典:Wikipedia)
北原 白秋(きたはら はくしゅう)は、本名を北原 隆吉(きたはら りゅうきち)といいます。生年は明治18年、没年は昭和17年(1942年)です。詩人、童謡作家、歌人として活躍しました。
北原白秋は、福岡県の酒造業を営む家に生まれました。10代半ばに文学に目覚め、雑誌『明星』に傾倒しました。明治37年(1904年)早稲田大学英文科予科に入学、上京します。早稲田大学では、同郷であることもあって、若山牧水と親しくなります。与謝野鉄幹が創立し、雑誌『明星』を発行していた新詩社に明治39年(1906年)に参加、与謝野鉄幹、晶子、石川啄木らと知り合いました。
文壇に人脈を広げつつ、西洋的なものに親しみ、明治41年(1908年)、新詩社を脱退、パンの会に入り、その中心人物となります。パンの会とは、明治の末期に、若手の芸術家が集った集まりです。
明治42年(1909年)には処女詩集『邪宗門』を発行、官能的、唯美的な詩風が話題となりました。初めての歌集は大正2年(1902年)の『桐の花』で、抒情的でロマンチシズムあふれる短歌が多く収録され、北原白秋は歌壇でも存在感を見せます。
その後も数々の詩集、歌集を発表しました。童謡の作詞家としても名高く、「ゆりかごのうた」や「雨降り」など、北原白秋が作詞した、抒情的で優しく美しい言葉の童謡の数々はは今でも歌い継がれています。
晩年は糖尿病、腎臓病に悩まされ、療養しながら筆を取りましたが、昭和17年(1942年)57歳で逝去しました。
「北原白秋」のそのほかの作品

(北原白秋生家 出典:Wikipedia)
- 君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ
- 春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕
- しみじみと物のあはれを知るほどの少女となりし君とわかれぬ
- ヒヤシンス薄紫に咲きにけりはじめて心顫ひそめし日
- 廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける
- 手にとれば桐の反射の薄青き新聞紙こそ泣かまほしけれ
- 草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり
- ひいやりと剃刀ひとつ落ちてあり鶏頭の花黄なる初秋












